日本の高速鉄道である新幹線は移動に便利ですが、その運賃は距離に応じて高額になりがちです。特に、家族旅行では、「子どもの分の料金が何歳から必要になるか?」によって旅費が大きく変わります。
本記事では、「新幹線は何歳まで無料か」という疑問に答え、年齢に応じた割引ルールや、幼児と新幹線に乗る際の注意点について、公式情報をもとに詳しく解説します。
新幹線は何歳まで無料?
結論から言えば、新幹線は小学校入学前の未就学児であれば、大人の同伴を条件に無料で乗車できます。小学校入学前の子どもはJRの区分上「幼児」にあたり、おとなに同伴されて指定席やグリーン席等の座席を利用しない場合に限り無料で新幹線に乗ることが可能です。

年齢で言えば、無料で乗車できるのは「小学校に入学する前まで」、目安としては5歳以下の子どもということになります。この幼児無料のルールはJR東日本・JR西日本など全国共通で、新幹線を含むJR線全体で適用されています。
ただし、JRでは料金区分を実際の年齢ではなく「学校への在籍状況(学齢)」で判断しています。例えば、6歳でも誕生日の関係でまだ小学校に入学していない子どもは幼児扱いとなり無料の対象に含まれます。逆に、12歳でもまだ小学生であれば「こども」扱いとなり、子ども料金で乗車できます。
ただし、大人1人が無料で同伴できる幼児は2人までで、3人目からは子ども料金のきっぷを購入する必要があります。
新幹線の年齢による割引のルール
新幹線の運賃・料金は年齢区分によって大きく3つに分かれています。
以下に区分と対象年齢をまとめます。
※ 「学年」と「年齢」で扱いが変わる注記に注意(例:12歳でも小学生は「こども」扱い、6歳でも未就学は「幼児」扱い)。
| 区分 | 年齢範囲 | 解説 | 参考 |
|---|---|---|---|
| おとな | 12歳以上 | 原則12歳以上。ただし12歳でも小学生は「こども」扱い(学年優先の特例)。 | jre-travel.com |
| 子ども | 6歳〜12歳未満 | 小学生相当の年齢帯。6歳でも小学校入学前は「幼児」扱い(未就学の特例)。 | jre-travel.com |
| 幼児 | 1歳〜6歳未満 | 小学校入学前まで。条件により無料乗車の扱い等が異なるため、同行者数や座席利用の有無に留意。 | jre-travel.com |
| 乳児 | 1歳未満 | 生後0歳。幼児と同様に無料扱いの範囲や指定席利用時の取り扱いは別途規定あり。 | jre-travel.com |
上記のように、小学生の年齢(6~11歳)が「子ども料金」、未就学児(およそ0~5歳)が「幼児」として扱われます。なお、こうした区分の適用は毎年4月1日を境に切り替わります。たとえば、その年の4月から小学生になる子どもは4月1日以降の乗車では「こども」として扱われ、子ども料金が必要になります。
小学生の新幹線料金は基本的に大人料金の半額です。乗車券や特急券(指定席券を含む)などはすべておとなの約50%の金額で購入できます。ただし、グリーン車の料金やグランクラスの料金など一部の特別車両・座席に関しては、子どもであっても割引が適用されず大人と同額になる点に注意が必要です。
例えば、東京~新函館北斗間(東北・北海道新幹線)を通常期に普通車指定席で利用する場合、運賃と特急料金の合計額は大人23,430円に対し、子どもは11,710円とほぼ半額に設定されています。東京~軽井沢間では大人6,020円に対し子ども3,010円と、同じく半額です。
ちなみに、この子ども半額の制度により、小学生までの子ども連れ旅行は飛行機より費用を抑えやすいメリットもあります。航空会社によっては子ども料金の設定がない場合もあり、仮にあっても適用年齢は多くが11歳までです。そのため、条件次第では飛行機よりも新幹線を利用することで家族の旅費を賢く抑えられるケースが多いと言えるでしょう。
幼児と新幹線に乗る時の注意点
未就学児の子ども(幼児・乳児)を連れて新幹線に乗車する際、料金面で注意すべきポイントがいくつかあります。ここからは、その代表的な注意点を3つ説明します。
注意1:幼児が座席を単独で使用する場合は子ども料金が必要
幼児は大人の膝の上に座るなど座席を占有しない場合に限り無料になりますが、自分専用の座席を使う場合には無料にはなりません。これは、例えば幼児の分の指定席を別途確保したり、幼児がグリーン席・寝台等を1人で利用したりするケースに該当します。
実際、JRの規定でも「幼児(乳児)が1人で指定席、グリーン席(自由席グリーン車を除く)等を利用する場合」は子どものきっぷが必要になると明記されています。
また、幼児を無料で乗せる場合は大人と同じ座席を共有することになるため、長距離の移動や混雑時には注意が必要です。繁忙期などで自由席が満席の場合、幼児を膝の上に抱えたまま長時間過ごすのはお子様にも保護者にも負担となります。確実に座席を確保して快適に移動したい場合は、たとえ未就学児でも事前に指定席を予約して子ども料金のきっぷを購入することを検討しましょう。
注意2:大人1人につき幼児2人まで無料(3人目から有料)
幼児を無料で同伴できる人数にも制限があります。おとなまたは子ども1人につき、無料で同伴できる幼児は2人までです。言い換えれば、3人目以降の幼児については子ども料金のきっぷを購入しなければなりません。
なお、無料扱いとなる幼児については乗車券類を別途用意する必要はありません。大人のきっぷ(乗車券・特急券など)だけで2人までの幼児を同時に乗車させることができます。3人目から初めて子ども用の乗車券を購入する必要が生じるという形です。
このルールは、例えば大人1人で幼児3人を連れて新幹線に乗る場合、3人目の幼児には子ども運賃が発生することを意味します。一方で、大人2人で幼児3人を連れているようなケースでは、それぞれの大人が2人ずつ幼児を無料同伴できるため、幼児3人全員を追加料金なしで乗車させることも可能です。
実際の家族旅行でも、自分の子ども以外に甥や姪を含め大人数の幼児を引率する場合などは、この人数制限に留意してください。JR各社の公式規定にも「『おとな』または『こども』1人に同伴される幼児が3人以上の場合、3人目からこどもの運賃・料金が必要」と明示されています。
注意3:幼児だけで乗車する場合は子ども料金が必要
幼児が保護者や年長の兄弟姉妹などに同伴されず、幼児だけで新幹線に乗る場合は、たとえ、年齢が未就学児であっても無料にはなりません。JRの規定でも「幼児が単独で旅行する場合」は子ども料金が必要なケースとして挙げられています。
実際には未就学児が一人で新幹線に乗るケースはあまり想定されませんが、例えば幼い子どもを単独で新幹線に乗せて祖父母の家まで行かせるような場合には、無料ではなく子ども用の乗車券・特急券類を購入する必要があります。また、小学生未満の兄弟だけで新幹線に乗車する場合も、大人の同伴がなければそれぞれに子ども料金が必要となる点に注意しましょう。
幼児は条件付きで無料になる
新幹線では、小学校入学前の幼児であれば所定の条件下で無料で乗車でき、それ以上の子ども(6~12歳の小学生)は子ども料金(大人運賃の半額程度)が適用されます。
ただし、幼児を無料にするには「同伴者1人につき幼児2人まで」「幼児が座席を単独利用しない」などのルールを守る必要があります。
これらの年齢区分にもとづく規則を理解しておけば、余計な交通費をかけずに済み、家族旅行を安心して楽しめるでしょう。実際に新幹線を利用する際は、最新の情報をJR各社の公式サイトなどで確認し、ルールに従ってお得に新幹線を活用してください。
参考文献
- JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)公式サイト – 「おとなとこども(きっぷあれこれ)」: https://www.jreast.co.jp/kippu/06.html
- JR西日本(西日本旅客鉄道株式会社)公式サイト – 「小学校入学前のこども(幼児・乳児)は、乗車券は必要ないですか。」(よくあるご質問): https://faq-support.westjr.co.jp/hc/ja/articles/8879896786447
- JR東日本 びゅうトラベル – 「新幹線のこども料金は何歳から必要?こども料金をお得にする方法」: https://www.jre-travel.com/article/00140/
- ツギツギ(東急)- 「新幹線の自由席を子どもは無料で使える?基本ルールや混雑時の注意点を解説」: https://tsugitsugi.com/tsugitsugi_style/article/topic-shinkansen-unreservedseat-children/


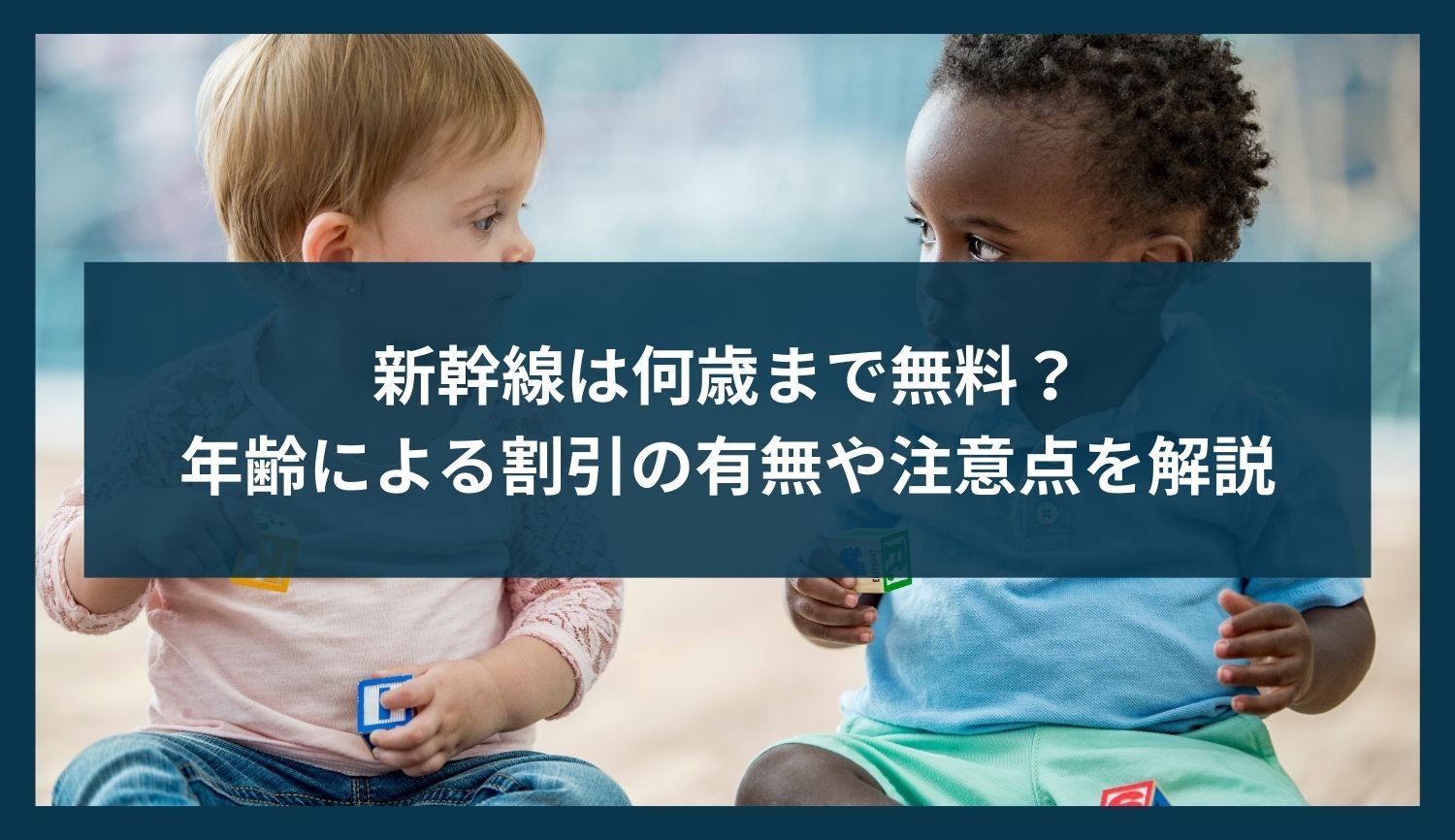
コメント