飛行機に乗る前に発熱していると、空港の検査でそれがばれてしまうのか心配する方は少なくありません。近年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、空港での検温体制が強化されてきました。
本記事では、空港で実施されている体温チェック(サーモグラフィ)の仕組みや、発熱が判明した後の搭乗拒否など航空会社の対応、さらに体温を感知するシステムについて詳しく紹介します。
飛行機で熱があるのはばれる?
多くの場合、飛行機に搭乗しようとして熱があると空港の検査で発覚します。空港の主要ターミナルでは出発前に赤外線による体温測定が行われており、37.5℃以上の高い体温が検知されれば追加チェックの対象になります。
特に、羽田や成田など主要6空港ではサーモグラフィーによる一斉検温が導入されており、他の空港でも体調不良の旅客がいれば個別に検温が実施されます。つまり、搭乗前の保安検査場で非接触の温度センサーにより発熱は把握されるため、基本的に熱があることはばれると考えてよいでしょう。
もっとも、2023年に新型コロナの感染症分類が緩和されて以降、国内線では全乗客に対する一律の検温は順次縮小されました。ただし、油断は禁物です。現在でも空港係員は旅客の健康状態に目を配っており、明らかに発熱の症状が見られる場合はその場で検温をお願いされます。
なお、国際線では入国時の検疫にてサーモグラフィによる発熱チェックが継続されています。厚生労働省の検疫情報によれば、入国者全員に対し赤外線カメラで発熱の有無を確認し、発熱や咳など症状がある人にはさらに詳細な聞き取りや必要に応じた検査が行われます。
熱があるとばれた後はどうなる?
搭乗前の検査などで熱があると判明した場合、航空会社の判断で搭乗を見合わせる措置が取られることが一般的です。航空各社は安全確保のため、他のお客様に感染を広げる恐れがある旅客については原則として搭乗をお断りする規定を定めています。
具体的には、インフルエンザや新型コロナなど感染力の強い疾病で定められた出席停止期間中に該当する方は航空機への搭乗は不適格とされ、医師から「感染の恐れがない」との証明が得られない限り搭乗できません。
そのため、空港での検温で発熱が確認されれば、搭乗手続きの段階で搭乗拒否もあり得ます。実際、日本航空(JAL)も「発熱がある方は、ご搭乗をお断りする場合があります」と明言しています。
搭乗見合わせを求められた場合の対応としては、予約便の変更やキャンセルを行うことになります。航空会社によっては、当日その場での搭乗拒否となっても柔軟な救済措置があります。たとえばJALやANAでは、急な病気や発熱で予約便に乗れない場合に医師の診断書を提出すれば、キャンセル料なしで日程の変更や払い戻しに応じてもらえます。
同行者も含め手数料なしで対応してくれる制度があるため、発熱時は無理に搭乗しようとせず、まず航空会社に連絡を取りましょう。LCC(格安航空会社)の場合でも、ピーチ航空などが公式サイトで発熱による予約変更・払戻しの案内を出しています。事前に連絡と医師の証明があれば費用負担を軽減できるケースが多いので、諦めず確認することが大切です。
一方、飛行機搭乗後に機内で発熱が判明した場合も考えられます。機内では乗務員が旅客の体調異変に気付けば迅速に対応します。具体的には、近くの席から離して座らせる、マスクを配布する、水分補給を促すなどの応急対応が取られます。
飛行機で熱があることを感知する仕組み
空港や機内で乗客の発熱を感知するには、赤外線技術を用いた非接触型の体温測定機器と人の目による観察が組み合わされています。現在、多くの空港では保安検査場の入口などに赤外線サーモグラフィー装置を設置し、通過する乗客の表面体温をリアルタイムでスキャンしています 。
サーモグラフィーとは温度を画像として可視化するカメラの一種で、物体(人)の表面から放射される赤外線の強さを検知し、それを温度情報に変換する仕組みです。多数の赤外線センサー素子で一度に広範囲を測定できるため、体温の高い人が映像上で色分けされて表示され、発熱者を瞬時に見つけ出せます。
設定されたしきい値を超える温度が検知されるとアラーム表示が出るタイプが一般的で、空港スタッフがその人物に声をかけ、詳細な体温測定をお願いする流れです。追加の体温チェックには、額や耳で測るハンディタイプの電子体温計(非接触型)や医療用の体温計を用いて正確に検温します。
機内においては、座席に座った乗客の体温を機械が自動で測定するような装置は通常ありません。機内での発熱感知は乗務員の目視と旅客からの申告に依存します。客室乗務員は乗客の様子(顔色や発汗、震えなど)を注意深く観察する訓練を受けており、体調不良が疑われる方には声をかけて状態を確認します。
乗客自身も無理をせず、寒気や熱っぽさを感じたら早めに乗務員へ知らせましょう。近年、一部の航空で実証実験されているIoT技術として、ウェアラブルセンサーで乗客のバイタルサインをモニタリングする試みもありますが、一般の商業飛行で普及した例はまだありません。
したがって、現状では、空港設置のサーモグラフィーによる検温が発熱感知の中核であり、機内では人的なケアで補完している形になります。
ばれると考えた方が良い
飛行機に乗る際、発熱があれば基本的に空港での検温によってばれると考えておきましょう。特に37.5℃以上の熱がある場合は、航空会社から搭乗を見合わせるよう要請される可能性が高いです。
搭乗前に熱が分かった場合、無理に強行せず航空会社に連絡して予約変更や払い戻しの相談をすることをおすすめします。診断書の提出でキャンセル料が免除される制度も整っているため、適切に手続きを踏めば経済的な損失を減らすこともできます。
機内で急に発熱した場合も、乗務員が適切に対応し、安全に到着できるよう手配されます。空の旅では自身と周囲の安全を第一に考え、発熱時には「搭乗しない勇気」を持つことが大切です。体調管理を万全にして、安心して飛行機の旅を楽しみましょう。
参考文献
- 国土交通省航空局「航空便をご利用のみなさまへ」(2020年)https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr5_000035.html (取得日: 2025-09-07)
- 日本航空(JAL) OnTrip「ご搭乗前もウイルス対策を徹底。空港の安全対策の今」(2020年)https://ontrip.jal.co.jp/jalstyle/17372053 (取得日: 2025-09-07)
- 全日本空輸(ANA)公式サイト「感染症・インフルエンザに感染している恐れのあるお客様」(更新日不明)https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/flight_service_info/assist/medical-infection/ (取得日: 2025-09-07)
- 厚生労働省検疫所「検疫の流れ(空港における検疫)」(2023年)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54498.html (取得日: 2025-09-07)
- アズビル株式会社「サーモグラフィ」(2020年)https://www.azbil.com/jp/corporate/pr/atoz/thermography/index.html (取得日: 2025-09-07)
- 日本航空(JAL) FAQ「突然の怪我や病気で予約便に搭乗できなくなった場合、変更できますか。」(回答日不明)https://faq.jal.co.jp/app/answers/detail/a_id/31108 (取得日: 2025-09-07)


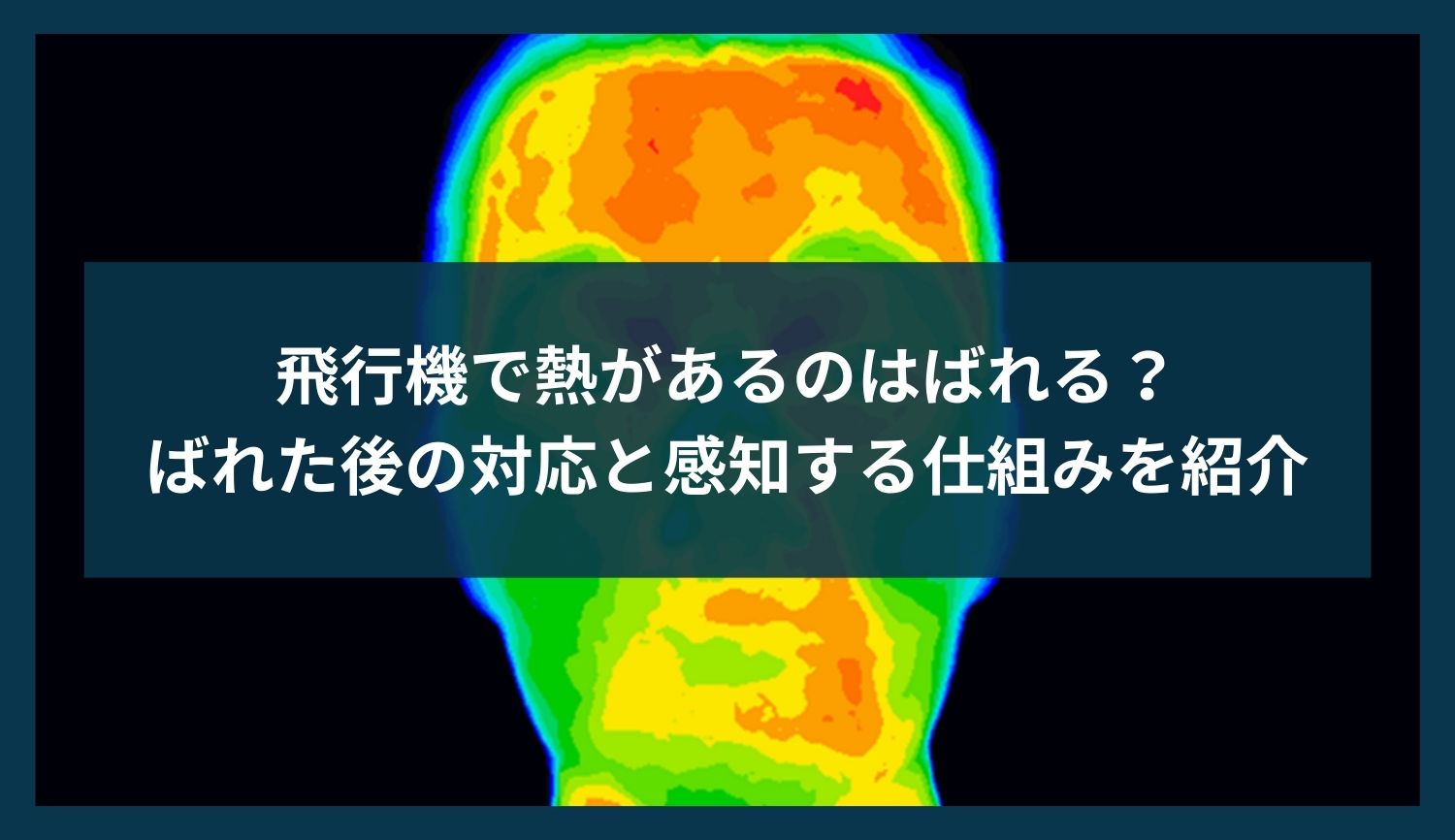



コメント