飛行機での旅行は便利ですが、乗り物酔いしやすい人にとっては不安の種でもあります。車や船と同様に揺れによって気分が悪くなる「飛行機酔い」に悩む方も少なくありません。「飛行機に乗るといつも酔う」「機内で気持ち悪くなったらどうしよう」と心配な方も多いでしょう。
せっかくの旅行が飛行機酔いで台無しにならないよう、事前にできる備えを確認しておきましょう。本記事では、飛行機で酔いにくい座席がどこか、酔いやすい人の特徴、さらには酔わないための対策や万が一酔ってしまった場合の対処法まで詳しく解説します。
飛行機で酔いにくい席はどこ?
機体中央付近の座席がもっとも酔いにくいです。 飛行機の重心は主翼付近にあるため、中央部は上下の揺れが少なく安定しています。これはシーソーの支点に近い部分に当たるため、両端が揺れても中央は振れにくいのです。
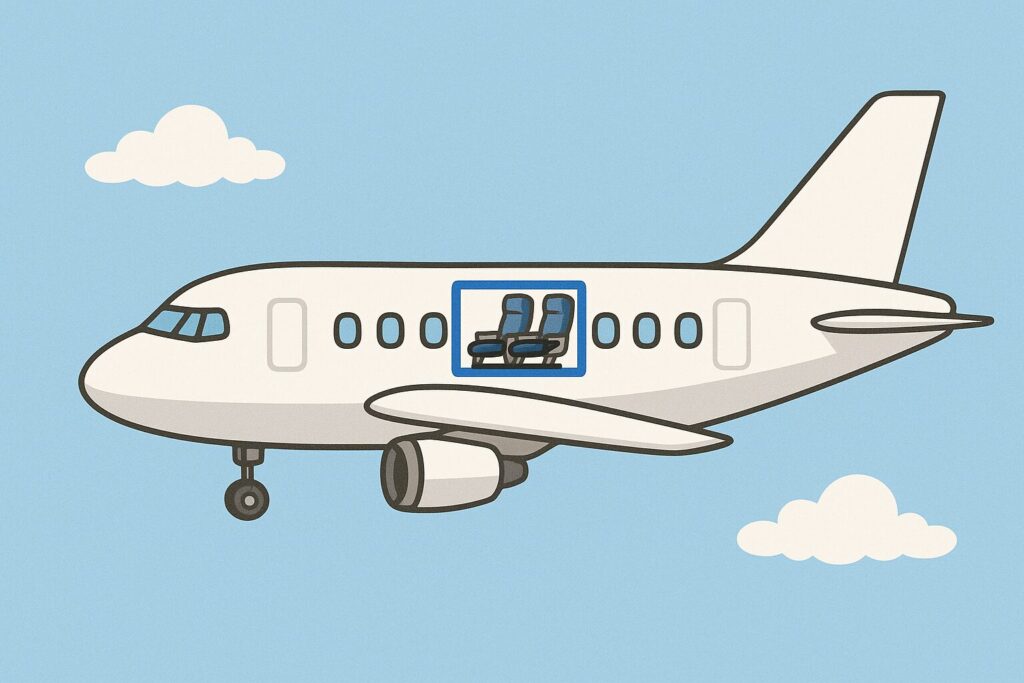
逆に、機体後方は重心から遠く揺れが大きくなる傾向があり、前方より最後部のほうがより揺れを感じやすいのです。そのため、揺れに敏感な人は主翼付近の中央の席を選ぶのがおすすめです。
なお、前方座席はエンジンより前側に位置するため比較的静かですが、重心からはやや離れるため揺れは中央ほど抑えられません。一方で後方座席はもっとも揺れやすいものの、空いていることが多くグループでも席を確保しやすいといった利点もあります。酔いにくさを最優先するなら中央付近の席を狙い、可能なら事前に座席指定しておきましょう。
なお、窓側席は外の景色を眺めて酔いを紛らわせやすい反面、気分が悪くなった際にすぐ立って移動しやすいのは通路側席です。自分の体質や不安に応じて、窓側・通路側も選択するとよいでしょう。
飛行機で酔いやすい人の特徴
飛行機酔いになるかどうかには個人差がありますが、予測できない乱気流による急な揺れで気分が悪くなる人がいます。
また、気圧の変化、睡眠不足やストレスなどの体調面の問題、「酔うかもしれない」という不安など精神面の緊張、機内のにおいや音、年齢など様々な要因が影響して酔いやすくなる場合もあります。
乗り物酔いは内耳(三半規管)で感じる揺れと視覚情報のズレによって自律神経が乱れることで起こりますが、酔いやすい人には次のような特徴が見られます。
一般的に子供のほうが乗り物酔いを起こしやすく、中学生頃に症状が出やすいピークがあり、成人すると経験を重ねることで軽減する傾向があります。ただ、大人になっても乗り物酔いに悩む人は少なくありません。
特徴1:精神的に緊張しやすい
飛行機に乗ることへの恐怖心や「また酔うのではないか」という強い不安を抱えている人は、酔いやすい傾向があります。
揺れに対する過度な心配は自律神経を不安定にし、ほんの少しの機体の揺れでも過敏に反応してしまいます。実際に、「揺れたらどうしよう」「酔うかもしれない」と考えすぎると精神的に不安定になり酔いやすくなるため、リラックスして構えることが大切です。
特徴2:体調やコンディションが万全でない
睡眠不足や疲労、空腹・満腹といった体調不良の状態だと酔いやすくなります。
前日にしっかり睡眠をとっておらず疲れていたり、飛行機搭乗前に食べ過ぎて胃が重い場合、あるいは逆に空腹すぎる場合は、自律神経のバランスが乱れやすく乗り物酔いの症状が出やすくなります。
普段は酔わない人でも、寝不足や空腹など体調が悪いときや機内の温度・臭いなど環境が影響して酔うこともあります。
特徴3:揺れや臭いに敏感で乗り物に慣れていない
もともと三半規管が敏感で車や船でも酔いやすい体質の人は、飛行機でも酔いやすいタイプです。
小さい頃から乗り物に乗る機会が少なく乗り物に不慣れな人も、大人になってから酔いやすくなる傾向があります。機内ではエンジン音や機内食の匂いなど刺激も多いため、そうした環境の変化に敏感な人も酔いやすいと言えます。
飛行機で酔わないためのおすすめの対策
飛行機酔いを防ぐには事前の準備と機内での工夫が重要です。
ここでは、酔いやすい人でも快適に過ごすための対策を3つ説明します。
方法1:搭乗前に十分な睡眠と適度な食事
フライト前日はしっかり睡眠をとり疲れを残さず、当日は満腹も空腹も避け、消化の良い軽めの食事を適度に摂ることが大切です。
また、機内では気圧低下により体内のガスが膨張しやすいため、炭酸飲料や豆類などガスが発生しやすい飲食物は控えめにするとよいでしょう。
胃に食べ物が残りすぎても空っぽでも気分不良の原因になるため、暴飲暴食やアルコールの飲み過ぎは控えましょう。締め付けの強い服装は血流を妨げて自律神経に負担をかけるため避け、体をリラックスさせた状態で搭乗しましょう。
方法2:酔い止め薬を事前に服用する
乗り物酔いしやすい方は離陸30分前に酔い止め薬を服用しておくことも有効です。
酔い止め薬には内耳の平衡感覚を抑える成分が含まれており、事前に服用しておけば「酔うかもしれない」という不安も和らぎます。
ただし、薬は眠気を誘う成分もあるため、服用後は無理に起きていようとせず体を休めましょう。なお、薬を避けたい場合は手首のツボ(内関)を刺激する酔い止めバンドを活用する方法もあります。
方法3:機内では視線を遠くに、読書は控える
機内での過ごし方も工夫しましょう。シートベルト着用サインが消えて飛行が安定したら、できるだけ遠くの景色を見るか目を閉じてリラックスし、スマホ画面や細かい文字を長時間見続けないようにします。
なお、揺れている最中に読書やスマートフォン操作をすると、目からの情報と内耳が感じる揺れとのズレが大きくなり酔いやすくなるため注意が必要です。
どうしても不安なときは早めにシートを倒して楽な姿勢をとり、首元にネックピローを当てて頭が揺れないように固定し、そのまま眠ってしまうのも有効で、飴玉を舐めたりガムを噛んで唾液を出すと気分転換になり、酔いにくくなる場合もあります。
酔ったらどうすればよいのか?
万全の対策をとっていても、実際に飛行機酔いしてしまうこともあります。気分が悪くなってきたら、早めの対処が肝心です。まず座席に深く腰掛けシートを少しリクライニングさせ、前かがみにならないようにしましょう。前傾姿勢でうずくまると胃が圧迫されてかえって吐き気が悪化するため、なるべく上体を起こし楽な姿勢を保ちます。
加えて、冷たい水や氷で口をすすいだり、頭や首筋を冷やすと自律神経の興奮が鎮まり楽になります。客室乗務員にお願いすれば冷たいおしぼりをもらえるので、額に当ててみるのもよいでしょう。飲み物では炭酸飲料(ジンジャーエールなど)を少しずつ飲むと吐き気が和らぐ場合もあります。
また機内の個人用送風口(エアベント)を開けて風を当てると換気され、気分がすっきりします。吐き気がどうしても収まらない場合は、無理をせず備え付けのエチケット袋を使いましょう。周囲に遠慮する必要はありません。
吐きそうなときは早めに乗務員に伝え、必要な処置やケアをお願いすることも大切です。短時間でも横になれそうなら後方の空いた席に移る提案をしてくれる場合もあります。適切な対処をすれば症状は徐々に落ち着いてきますので、深呼吸して焦らず対処しましょう。
正確な知識で対処しよう
飛行機で酔いにくい席は機体の中央付近で、重心に近いため揺れが小さく安定しています。反対に機体後方は揺れが大きいため、酔いやすい人はできるだけ避けましょう。また、飛行機酔いしやすい人には「不安を感じやすい」「睡眠不足や空腹時に弱い」「揺れや臭いに敏感」といった特徴があります。
酔わないためには事前の睡眠・食事などコンディションを整えることや、酔い止め薬の活用、機内での視線や姿勢の工夫など複合的な対策が有効です。特にフライト時間が長いほど酔ったときの身体的・精神的なダメージも大きくなるため、なおさら予防策を徹底しておくことが大切です。
それでも酔ってしまった場合は早めに楽な姿勢をとり、体を冷やす・換気するなど適切に対処すれば症状を和らげることができます。事前に対策を万全にし、万が一酔ったときの対処法も知っておけば、乗り物酔いは決して珍しいことではなく、正しい知識と備えがあれば過度に心配する必要はありません。酔いやすい方もポイントを押さえて準備すれば、安心して快適な空の旅を楽しめるでしょう。
参考文献
- テレビ朝日「飛行機で一番揺れない座席はどこ? 前方・中央・後方? その理由は…」(2024年7月30日)https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900006173.html (参照 2025-09-07)
- JAL Mall「『飛行機酔い』対策、教えます!」(2018年10月26日初稿、2022年10月18日更新)https://ec.jal.co.jp/shop/pages/tabicolumn14.aspx (参照 2025-09-07)
- 沢井製薬(サワイ健康推進課)「乗り物酔いは克服できるの? 対策を考える」(2022年3月)https://kenko.sawai.co.jp/theme/202203.html (参照 2025-09-07)
- ソラハピ「飛行機の揺れない席は『真ん中のちょっと前』!酔い予防と対処法も」(2023年7月4日)https://www.sorahapi.jp/column/post-3544/ (参照 2025-09-07)
- エスエス製薬(アネロン)「乗物酔いしやすい人とは?」(2023年10月2日更新)https://www.ssp.co.jp/aneron/cause/type.html (参照 2025-09-07)
- 大正製薬(センパア)「大人が乗り物酔いする理由とは?」https://brand.taisho.co.jp/semper/trivia/006/ (参照 2025-09-07)


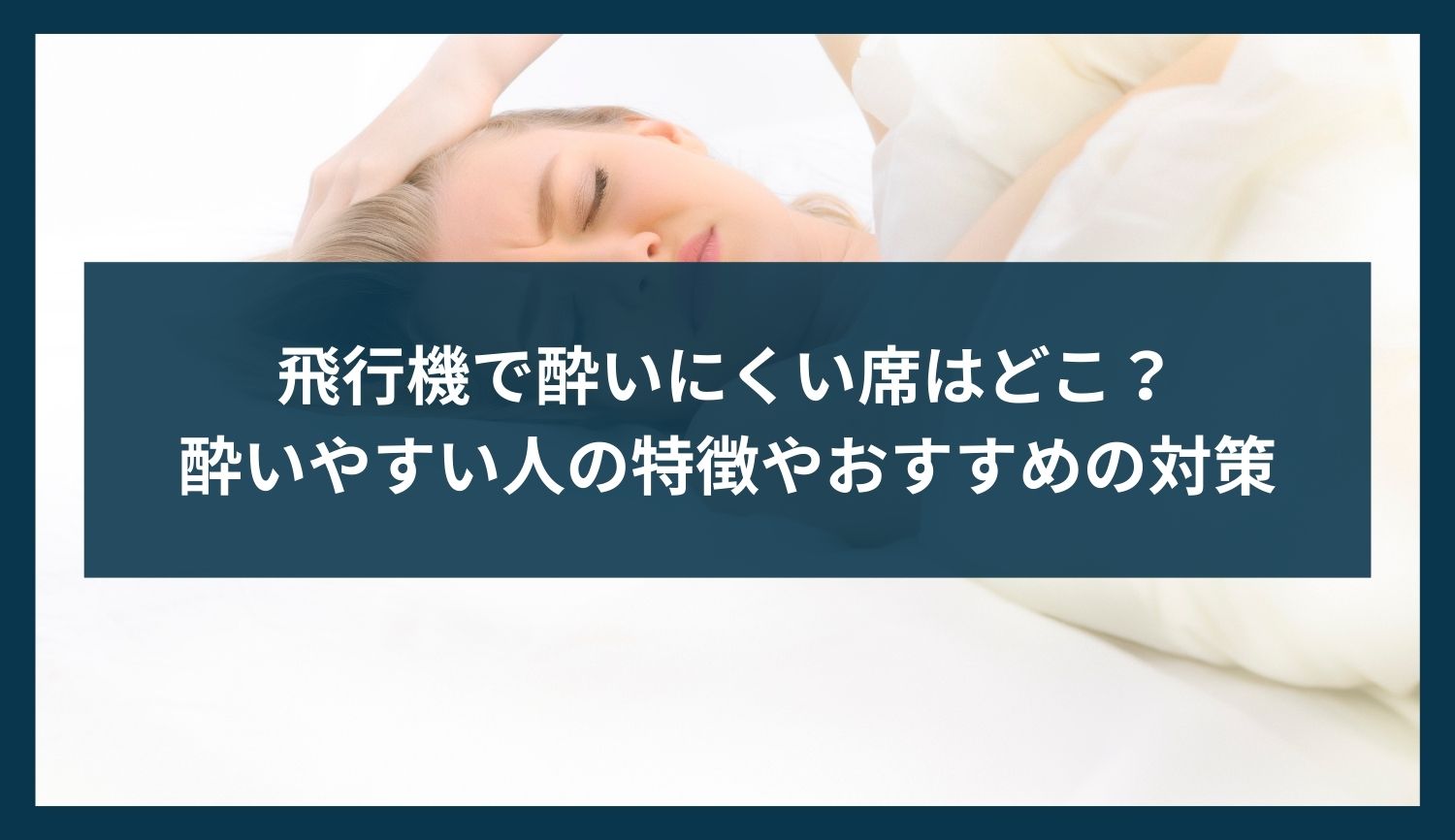




コメント