「飛行機が飛ぶ原理はまだ完全には解明されていない」という話を耳にして驚いた人もいるでしょう。飛行機が飛ぶ原理そのものは理論的に説明されていますが、空気の流れの複雑さから実験で細部まで完全に検証することが難しく、誤った通説も根強く存在するため、科学的には「未解明」と慎重に表現されるのです。この記事では、この理屈について詳しく言及しています。参考にしてみてください。
飛行機が飛ぶ原理とは?
飛行機が空を飛べるのは、翼が発生させる上向きの力によって機体の重さが支えられるからです。 これは航空力学・流体力学の分野で説明される現象で、翼の形状や角度により空気の流れ方が変化し、上下の圧力差と空気の流れの反作用によって揚力が生じます。
翼の上面を流れる空気は下面より速く、圧力が低くなるため上から下への押す力が弱まり、相対的に下面から上向きに押し上げる力が強くなります(ベルヌーイの定理)。同時に、翼が空気を下向きに押し下げることでその反作用で翼が上に押し上げられる現象(作用反作用の法則)も揚力に寄与しています。
これらの原理により飛行中の主翼には機体重量を上回る揚力が発生し、飛行機は空中に浮かび続けることができるのです。例えば、大型旅客機の主翼でも、離陸時には機体総重量(数百トン)以上の揚力を瞬時に生み出しています。翼による揚力の計算には複雑な流体方程式(ナビエ・ストークス方程式)を解く必要がありますが、実際には非圧縮性や粘性の無視などの近似で十分な精度の計算が可能であり、航空エンジニアはこれを用いて安全に機体設計を行っています。
飛行機が飛ぶ原理はまだ完全には解明されていないと言われる理由
科学的な厳密さと誤解の広まりという2点が、「飛行機が飛ぶ原理は未解明」と言われる理由です。 ここでは主な理由を2点、順に説明します。
理由1 理論はあっても実証が難しい
物理学では、理論的に説明できても実験で確認できていない現象は「解明された」とは言いません。飛行機の揚力自体は科学理論で説明可能ですが、空気の流れは非常に複雑であり、その細部までを実験で追跡して完全に再現・検証することは困難です。
そのため、物理学者たちは「原理は理論上わかっているが現実の細部までは実証できていない」という慎重な表現を用い、科学的な立場では「まだ解明されていない」という言い方になるのです。
理由2 誤った通説が広まっているため
もう一つの理由は、世間に流布した揚力の誤解です。飛行機の翼による揚力発生メカニズムについては簡易な説明が独り歩きし、「翼の上下の空気が同時に後端に到達するため上面の流速が上がり揚力が生まれる」という同時到着仮説などの誤った説が広く信じられてきました。
実際にはこの説明は正しくなく、専門の教科書や記事でも不正確な記述が多いことが指摘されています。このような背景から「飛行機が飛ぶ仕組みはまだよくわかっていないのではないか」という誤解が生じており、結果として未解明だと言われる一因になっています。
同時到着仮説:翼上面と下面を流れる空気が常に後縁で同時に合流するという仮定。実際には翼上面の空気は下面よりも後縁に早く到達しうることが実験で示されています。
飛行機が飛ぶ原理を研究している場所
飛行機の揚力や空力現象の解明・応用研究は、専門の研究機関や大学で日々進められています。
日本では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の調布航空宇宙センターがその代表例です。同センターはJAXAにおける唯一の航空技術研究拠点で、機体形状や素材の基礎研究から電動航空機・超音速機の開発まで航空分野の最先端研究を担っています。施設内には国内最大級の風洞(空気の流れを人工的に発生させて模型機に当てる実験設備)が整備されており、翼の模型に風を当てて周囲の空気の流れや圧力分布を測定し、揚力発生のメカニズムや機体の空力特性を研究しています。
一方、アメリカ航空宇宙局(NASA)でも航空工学の研究は重要な位置を占めています。例えば、バージニア州のNASAラングレー研究センター(旧NACAラングレー研究所)では、施設の約3分の2を航空機の研究に充て、航空機の性能向上や安全性検証のために40以上の風洞実験設備を運用しています。
この他にも各国の航空宇宙局、航空機メーカー(ボーイングやエアバス等)の研究部門、そして大学の航空工学科・流体力学研究室など、世界中の研究機関で飛行機が飛ぶ原理に関する調査・応用研究が続けられています。
近年は、スーパーコンピュータを用いた数値流体力学(CFD)シミュレーションによって空気の流れを精密に再現する試みも進み、従来は測定困難だった揚力発生過程の詳細解明や新しい翼設計への知見が深められています。
まとめ
飛行機が飛ぶ原理自体はクッタ・ジュコーフスキーの定理などによって1900年代初頭にはすでに理論的に解明されており、現代の航空機設計では揚力の計算も実用上問題なく行われています。
しかし、空気の流れの全容を実験で完全に裏付けることは難しいため物理学的には「未解明」と表現されることがあり、さらに広く流布した誤った翼の説明が「本当は飛ぶ理由がわかっていない」という誤解を生んだ側面もあります。
重要なのは、基本原理が理解されていないから飛行機が飛んでいるわけではないという点です。実際には理論と経験に裏打ちされた設計・試験によって飛行機は安全に飛んでおり、その背後には充分に確立された科学があります。
現在も風洞実験や数値シミュレーションによって揚力の細部や新たな航空技術の研究が続けられており、「未解明」と言われる部分も少しずつ明らかにされているのが現状です。飛行機はなぜ飛ぶのか――その答えは決して魔法や謎ではなく、科学的探究によって今後もより正確に理解されていくでしょう。
参考文献
- 工学院大学 金野祥久 (2022) 「飛行機はなぜ飛べるか」『月刊うちゅう』2022年11月号 4-9頁 (科学館HP掲載PDF) <https://www.sci-museum.jp/wp-content/uploads/2022/11/universe2211_4-9.pdf>(2025年9月6日取得)
- Nazology (2025) 「なぜ飛行機の飛ぶ理由は『未解明』と言われるのか?」(2025年4月27日) <https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/175916>(2025年9月6日取得)
- 荒瀬梨絵 (JAXA航空技術部門) (2025) 「航空宇宙の技術で未来をつくる。奥深大寺の研究所訪問記」 奥深OKUJIN (2025年2月27日) <https://okujin.com/jaxa/>(2025年9月6日取得)
- Wikipedia日本語版 (最終更新 2023-09-18) 「ラングレー研究所」<https://ja.wikipedia.org/wiki/ラングレー研究所>(2025年9月6日取得)
- Tidbits (りけいじん) (2023) 「飛行機が飛ぶ原理はわかっていないというのは本当か?」(初出2020年4月30日・更新2023年11月16日) <https://tbits.jp/airplane/>(2025年9月6日取得)


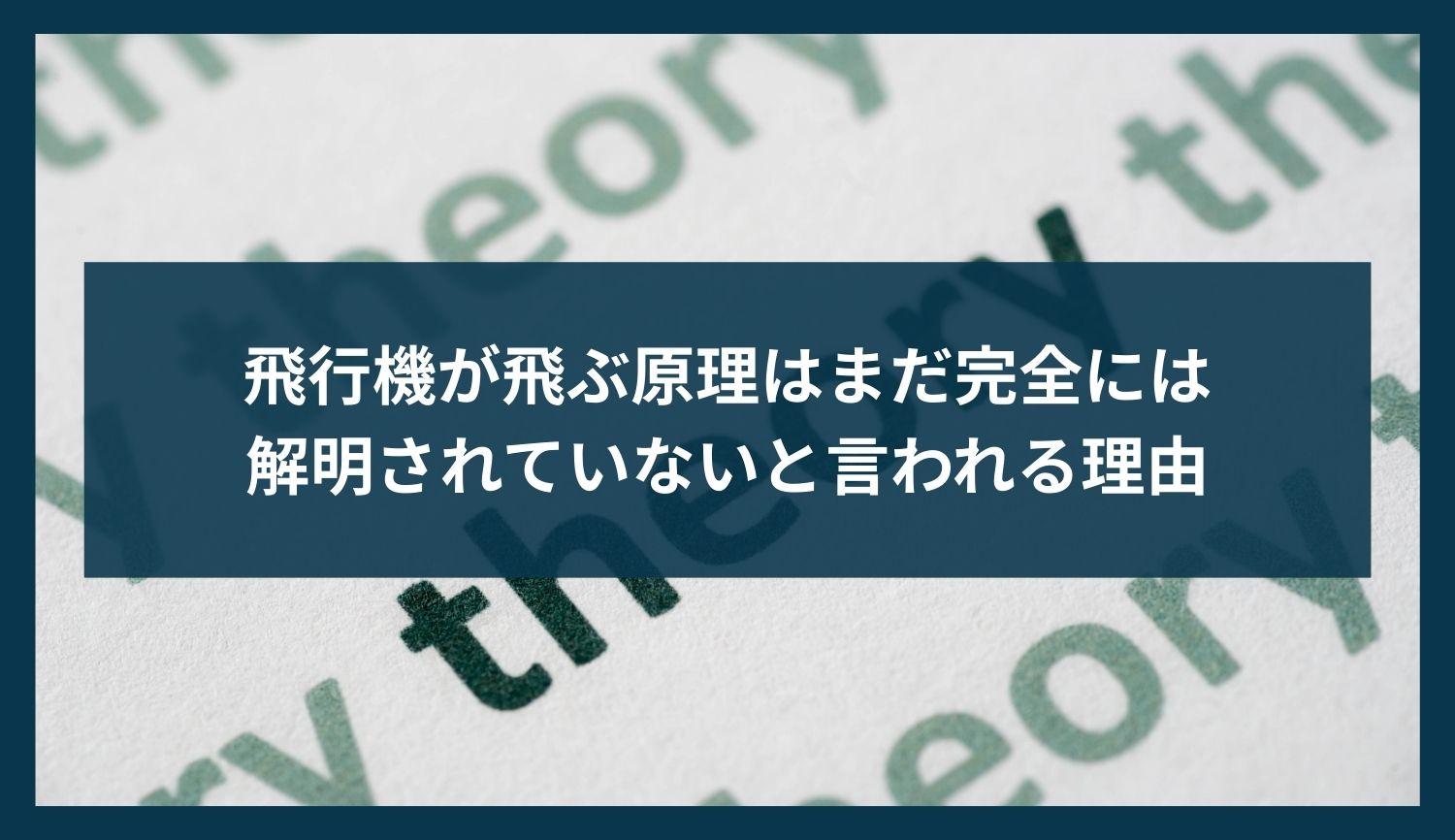
コメント