新幹線に乗った際の耳の詰まりは、急激な気圧変化による耳管機能の不具合が主要な原因です。この現象は医学的に解明されており、適切な対処法を知っておくことで、不快な症状を大幅に軽減することが可能です。
新幹線で耳が詰まる原因
新幹線で耳が詰まる現象の背景には、気圧変化による耳管の機能障害、個人の体質的要因、環境的な要因という3つの主要な原因があります。これから3つの原因について詳しく説明します。
原因1:トンネル通過時の急激な気圧変化
新幹線で最も耳の詰まりを感じやすいのは、トンネル通過時の急激な気圧変化です。電車がトンネルに高速で進入すると、まずトンネル内の空気が圧縮されることで、鼓膜が中へ押し込まれます。その後、トンネルと車両の間で気流の速度差が発生し、車内の気圧が低下することにより、今度は鼓膜が外へ引っ張られるようになります。
山梨大学工学部の研究によると、新幹線の場合には窓側の壁が車内側に少し膨らんで(車体が潰れて)車内の気圧が上がることが確認されています。実際に気圧計を用いた測定では、新幹線の先頭では気圧が高くなり、後尾では気圧が低くなっていることが実証されています。
この急激な気圧変化により、耳の鼓膜を境に気圧差が生まれ、鼓膜に力がかかって「ツーン」となる症状が発生します。
原因2:耳管の構造的・機能的問題
耳の詰まりやすさには、個人の耳管の構造や機能に大きな個人差があります。耳管は鼻腔(鼻の奥の空間)と耳の奥をつなぐ管で、普段は閉じているのですが、唾を飲み込むことなどで開き、鼓膜の内外の気圧を調整する重要な役割を果たしています。
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会によると、耳管狭窄症の患者では、風邪に伴う急性鼻炎、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、上咽頭炎などの鼻の炎症により耳管の開閉機能が低下し、電車のトンネルに入った時のような耳の詰まり感が慢性的に続くことがあります。
また、耳管開放症の場合は、耳管が開きっぱなしになっているため、気圧変化に対してより敏感に反応し、自分の声が響いて聞こえたり、呼吸音が耳に響いたりする症状が現れます。
原因3:体調や環境要因
新幹線での耳の詰まりは、体調や周囲の環境によって悪化することが知られています。風邪やアレルギー性鼻炎にかかっている場合は、普段よりも耳管が詰まりやすい状況にあるため、通常よりも気圧の調整がしにくくなってしまいます。
国立感染症研究所検疫所の資料によると、睡眠不足や二日酔いなどの場合も、耳の痛みなどの不快感を覚えやすくなることが報告されています。また、飲酒は耳管周囲の粘膜を腫らせ、眠ってしまうと唾を飲み込む回数が減るため、気圧調整機能が低下します。
さらに、急激な体重減少や妊娠、ストレスなども耳管機能に影響を与え、新幹線での耳の詰まりを感じやすくする要因となります。
新幹線で耳が詰まった時の対処法
新幹線で耳が詰まった際には、即効性のある耳抜き方法、自然な耳管開放を促す動作、物理的な圧力調整という3つの主要な対処法が有効です。これから3つの対処法について詳しく説明します。
方法1:バルサルバ法による耳抜き
バルサルバ法は最も一般的で効果的な耳抜き方法です。この方法は、口を閉じた状態で鼻をつまんで、鼻をかむときのイメージで少しずつ息を吐き出すことで行います。
日本の医療機関では、両方の鼻をしっかりつまんで、口を閉じて鼻をふくらませるように軽く何度か試みることが推奨されています。うまくいけば、プシューッという音とともに耳管が開き、気持ちがよい瞬間を感じることができます。
ただし、強くやりすぎると鼓膜に傷をつけてしまうこともあるため注意が必要です。特に鼻が悪い時や痛みがある時は慎重に行い、改善されない場合は無理をせず他の方法を試すことが重要です。
方法2:唾液分泌を促進する方法
飴を舐めたりガムを噛んだりすることで、自然に唾を飲み込む回数を増やす方法も非常に効果的です。つばを飲み込むことで耳管が開くため、症状が改善されやすくなります。
一掌堂治療院の専門家によると、新幹線では「飲食以外のときは、ガムを噛むか、あめをなめる」ことが推奨されています。また、意識的にあくびをしたり、アゴを上下左右に動かしたりすることも効果があります。
この方法は、正式にはフレンツェル法と呼ばれ、あめやガムをかんでつばを多く出してごくりと飲み込むだけの簡単な方法です。つばを飲み込む時に耳管が開くメカニズムを利用した、最も自然で安全な対処法といえます。
方法3:気圧対応型耳栓の使用
気圧変化を和らげる効果のある飛行機用の特殊な耳栓も、新幹線での耳の詰まりに有効です。通常の耳栓とは異なり、耳栓に気圧調整用の弁を設けることで、外(車内)の気圧の変化の影響を急激に受けないようにし、鼓膜への負担を軽減する仕組みになっています。
サイレンシア フライトなどの製品は、鼓膜にかかる気圧変化を緩やかにし、耳の不調を未然に防ぐ効果があります。実際の使用者からは「いつもの耳鳴りやツンとした痛み、耳が遠くなる感覚はどこへ消えたのかと思うほど」効果的であったとの報告があります。
新幹線でも、トンネル通過時の急激な気圧変化に対して同様の効果を発揮し、長時間装着していても耳穴が痛くならないという利点もあります。
耳の詰まりを防止するにはどうすればいい?
新幹線での耳の詰まりを事前に防ぐためには、体調管理による予防、座席選択と姿勢の工夫、事前準備による対策が重要です。
体調管理による予防
最も重要な予防策は、乗車前の体調管理です。風邪やアレルギー性鼻炎の症状がある場合は、事前に治療を行っておくことが効果的です。日本の医療機関では、搭乗時に症状が和らいでいる状態になっているように薬を調整して飲んでおくことが推奨されています。
また、十分な睡眠と水分摂取、適切な体重管理も耳管機能の正常化に重要です。飲酒は耳管周囲の粘膜を腫らせるため、新幹線利用の前日は控えめにすることが望ましいです。
座席選択と移動中の対策
座席の選択も予防に効果的です。一掌堂治療院の推奨によると、「座席は、なるべく進行方向に向って左の通路側」を選ぶことが良いとされています。これは、気圧変化や振動の影響を最小限に抑える効果があると考えられています。
また、仮眠するときは耳栓をすることも重要な予防策です。睡眠中はつばを飲み込む回数が減ってしまうため、耳管が気圧を調整しにくくなってしまうからです。
事前準備と持参品
新幹線利用前には、以下の準備を行うことが推奨されます:
特に気圧対応型耳栓は、100円ショップで購入できる手軽なものから、数千円ほどするものまでさまざまな種類があり、事前に用意しておくと安心です。
異変を感じたら病院に行こう
新幹線での耳の詰まりは、主にトンネル通過時の急激な気圧変化によって引き起こされる生理学的な現象です。この症状は個人の耳管機能や体調によって大きく左右され、適切な対処法を知っておくことで効果的に軽減できます。
対処法としては、バルサルバ法による耳抜き、飴やガムによる唾液分泌促進、気圧対応型耳栓の使用が特に有効であることが医学的に確認されています。
予防においては、事前の体調管理と適切な準備が重要です。風邪やアレルギー症状がある場合は事前治療を行い、気圧対応型耳栓やガムなどを準備しておくことで、快適な新幹線移動が可能になります。
もし症状が長時間続いたり、激しい痛みを伴ったりする場合は、航空性中耳炎に類似した状態の可能性があるため、速やかに耳鼻咽喉科を受診することが重要です。適切な知識と準備により、新幹線での移動をより快適に楽しむことができるでしょう。


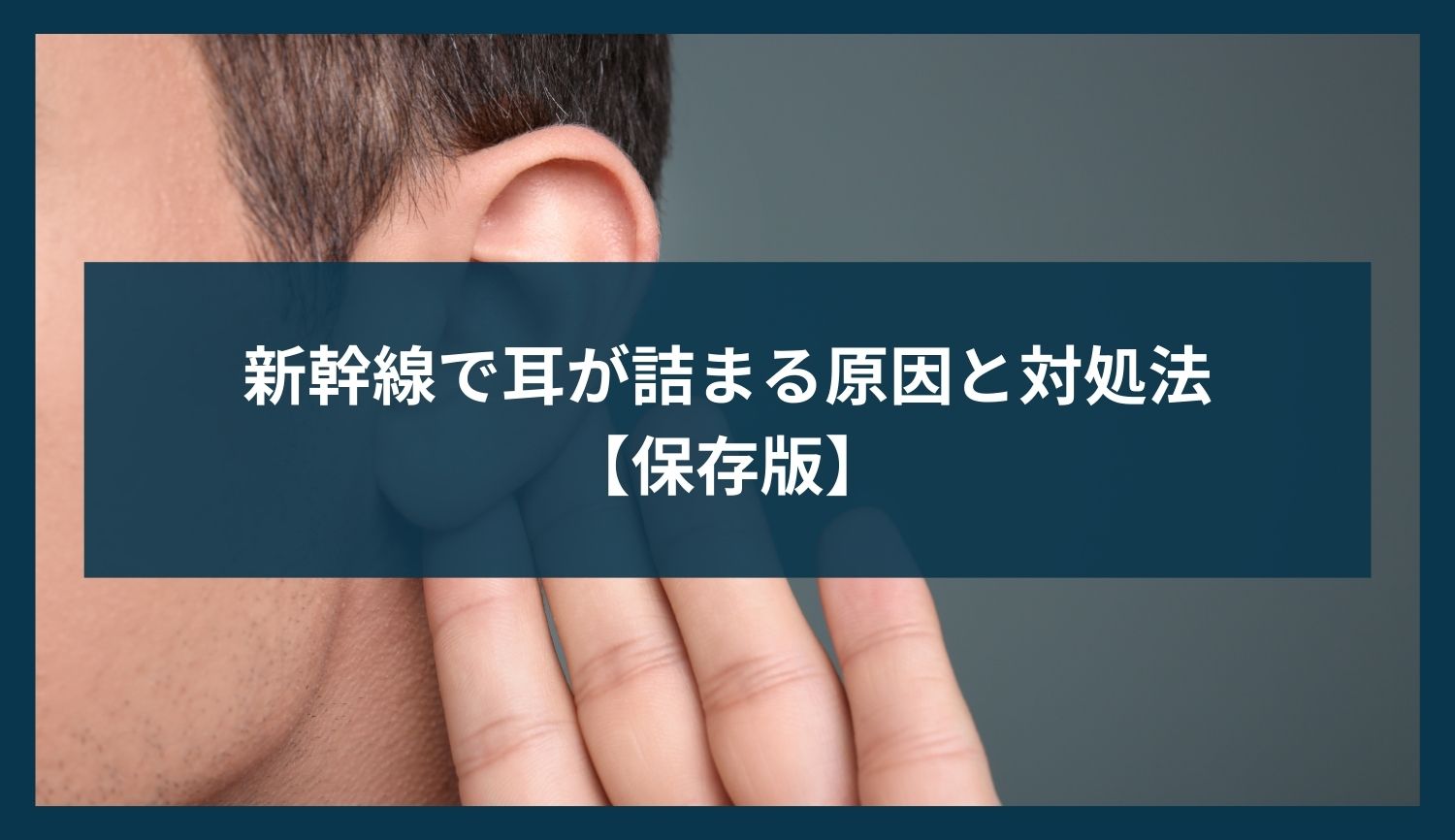

コメント