新幹線は日本全国を高速で結ぶ便利な交通手段ですが、乗車中にスマートフォンなどの電波が悪くて困った経験はありませんか?仕事でメール送受信やオンライン会議をしたいとき、また動画視聴などで時間を過ごしたいときに通信が不安定だとストレスを感じるでしょう。
本記事では、新幹線で電波が悪くなる原因を詳しく解説し、その上で電波状況を少しでも良くする対処法を紹介します。事前に対策を知っておくことで、新幹線での移動時間をより快適に過ごせるようにしましょう。
新幹線の電波が悪い原因
新幹線で通信環境が不安定になる背景には、いくつかの要因が考えられます。ここでは、新幹線で電波が悪くなる主な原因を3つ説明します。
原因1: 高速走行による基地局切替の頻発で通信が不安定に
新幹線は時速200~300kmもの高速で走行します。その間、スマートフォンは常に近くの携帯基地局と通信し続けますが、移動速度が非常に速いため基地局との接続先が次々と切り替わります。この高速移動中の頻繁なハンドオーバーにより、タイミングによっては通信が一時的に途切れることがあります。
また、新幹線は屋外を高速移動しているため、周囲の建物や地形など環境が刻々と変化し、安定した電波が届きにくくなる場合があります。例えば、駅に停車中は駅構内の基地局を掴みますが、駅の構造によって車内まで電波が十分届かないケースもあります。
高速移動そのものが通信の乱れを生みやすい要因となっており、「走行中はスマホの通信が遅い」と感じる現象につながっています。
原因2: トンネルや山間部など電波が届きにくい区間が存在
新幹線の路線には、長大なトンネルや山あいの地域を通過する区間が多く含まれます。こうした場所では地上の基地局電波が物理的に遮られ、電波が届きにくいことが以前はよくありました。実際、少し前までは「トンネルに入ると通信が途切れる」のが当たり前で、トンネル区間は携帯電話の圏外になるケースが多々あったのです。
この状況を改善するため、総務省は「電波遮へい対策事業」という取り組みを推進し、トンネル内でも携帯電話が使えるように中継設備の設置を支援してきました。具体的に言うと、北海道新幹線では国の補助金を活用し、トンネル内に光ファイバーとアンテナを整備する工事を行い、2020年3月に新青森~新函館北斗間の全トンネル(約97km)で携帯電話が利用可能になりました。
さらに、2020年末には山形新幹線の残りトンネル工事も完了し、現在営業中の新幹線全線でNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの大手3社回線がトンネル内も含めて利用可能となりました。
このようにトンネル内の「圏外」は順次解消されてきていますが、それでも山間部など基地局の数が限られる地域では電波が弱く不安定になることがあります。特に、地方部を通る区間では地上局との距離や地形の影響で通信品質が落ちやすく、完全に防ぐことは難しいのが現状です。
原因3: 車両の構造と利用集中による通信品質の低下
新幹線車両そのものの構造や、車内での利用者の集中も電波状況に影響を与えます。
まず、新幹線の車体は安全性や空力性能のため多くが金属で覆われています。金属製の外板は電波を通しにくいシールド効果を持つため、外部の電波が車内に届きにくくなる傾向があります。
携帯電波は主に窓から入るとされており、窓の有無や大きさで室内の電波強度が変わります。新幹線は高速化のため窓が小さめで車体の密閉性も高いため、車両中央や通路側の席では電波が減衰しやすいのです。実際、車内の場所によって通信状態が変わることがあり、「車両の中央にいると圏外になりがちだがデッキや窓際だとつながる」という声もあります。
次に、近年は新幹線車内で多くの乗客が一斉にスマホやPCでネット通信を行うようになりました。特に朝の通勤時間帯のビジネス客や、週末・連休の旅行客が多い時間帯には、一斉に大容量のデータ通信(動画視聴やファイルダウンロード等)が行われて回線に負荷がかかります。
利用者の集中によりモバイル回線が混雑(輻輳ふくそう)状態になると、通信速度の低下や接続の不安定さが生じます。実際、満員に近い車内では通信が遅くなったり繋がりにくくなったりすることが知られており、多数のスマホが密集することで電波の競合が発生してしまうのです。
新幹線の電波が悪い時に良くする対処法
新幹線で通信状態が悪くなっても、ちょっとした工夫でネット接続を維持したり快適さを向上させたりすることが可能です。ここでは、電波が悪いと感じた際に試せる対処法を3つ説明します。
方法1: 窓側の席を選んで電波を受信しやすくする
電波状況を少しでも改善するために、座席位置を工夫することは有効です。前述の通り車体の金属構造が電波を遮蔽するため、車両の中央や通路側より窓側の席の方がわずかに電波を拾いやすいとされています。実際、電波は主に窓から入る性質があるため、基地局の方向に窓があるほど室内(車内)まで電波が届きやすくなります。
そのため、新幹線に乗る際に指定席を取るのであれば窓際の席を選ぶことを検討してみましょう。
もちろん場所によって効果の差はありますが、トンネル区間や山間部など電波が不安定になりやすいエリアでは、窓側にいるだけでも通信状態が多少安定する場合があります。完全に途切れを防ぐことは難しくても、「圏外になりにくい席」を意識することでストレスを軽減できるでしょう。
なお、車内を移動できる状況であれば一時的にデッキ付近や窓側へ移動して通信するのも一つの手です。
方法2: 無料の車内Wi-Fiサービスを活用する
新幹線では現在、多くの路線・車両で無料の車内Wi-Fiサービスが提供されています。自分のスマホの電波がつながりにくいと感じたら、車内Wi-Fiに接続してみるのも有効な対策です。たとえば、JR東日本の新幹線では「JR-EAST_FREE_Wi-Fi」、東海道・山陽新幹線では「Shinkansen_Free_Wi-Fi」といったネットワーク名で誰でも無料利用可能なWi-Fiが整備されています。
車内Wi-Fiの使い方は各列車内の案内ステッカー等にも書かれていますが、基本的にはSSIDに接続後、ブラウザ認証ページで利用登録する流れです。
注意点として、1回の接続につき時間制限(東海道・山陽新幹線では30分間など)がある点があります。30分経過すると一度切断されますが、回数無制限で再接続は可能なので、引き続き利用したい場合は再度ログインすればOKです。長時間の乗車では少し手間ですが、これも多くの人に公平に帯域を提供するための措置です。
また、車内Wi-Fiの通信速度や安定性にも限界があります。新幹線Wi-Fiは各列車に搭載されたモバイル回線をバックホールとして利用しており、言わば「列車全体で一つの携帯回線をシェアしている」状態です。そのため、山間部やトンネルなどそもそも携帯電話が圏外になる場所ではWi-Fiも繋がりません。
方法3: スマホのテザリングやモバイルルーターで安定通信を確保する
社用PCのセキュリティ上の理由などで車内のフリーWi-Fiが使えない場合や、より安定した通信速度が必要な場合は、自分のスマートフォンのテザリング機能を利用する方法が便利です。
テザリングとは、スマホをモバイルWi-Fiルーター代わりにしてPCやタブレットをインターネット接続させる機能のことで、新幹線移動中のビジネスパーソンにも多く利用されています。現在、大手キャリア(NTTドコモ・KDDI(au)・ソフトバンク)の携帯回線であれば新幹線の全区間でほぼ途切れることなくサービスエリア内となっており、テザリングによって自前の安定したネット接続を確保しやすくなっています。
テザリングを活用するメリットは、自分専用の回線を使える点です。車内の共有Wi-Fiと異なり、自分の契約している回線の速度をそのまま利用でき、他人に帯域を奪われる心配がありません。特にNTTドコモなどエリアの広い回線をお持ちであれば、新幹線乗車中もトンネルを含め途切れにくいため、社用メールの送受信やオンライン会議も比較的安心して行えるでしょう。
まとめ:スマホのテザリングが便利!
新幹線で電波が不安定になる原因として、高速移動・トンネル・車両構造・利用集中といった要素を見てきました。完全に途切れを無くすのは難しいものの、ちょっとした工夫や準備で通信環境を改善することは可能です。
特に、スマホのテザリング機能は新幹線での強い味方です。大手キャリア回線なら全国の新幹線区間がサービスエリア内となっているため、自分のスマホさえ繋がっていればPCもインターネットに接続できます。社用PCでもテザリング経由ならセキュリティ上の制限を回避できる場合が多く、業務もスムーズです。テザリング利用時はスマホの電池消耗が激しいためモバイルバッテリーを携行する、通信量制限に注意するといった点に気を付けつつ、有効に活用してみてください。
新幹線での移動時間は工夫次第で快適なネット活用タイムに変わります。事前に対策を知り準備することで、「電波が悪くてイライラ…」を減らし、旅や出張をより充実した時間にしていきましょう。
参考資料・出典:
- 総務省・JR各社によるトンネル内携帯電話不通区間解消の取組jrhokkaido.co.jpjrhokkaido.co.jpasahi.com
- NTTドコモ公式サイト 「電車の中だとつながりにくいことがあるのはなぜ」docomo.ne.jpdocomo.ne.jp
- NTTドコモ公式サイト 「室内での電波の入りやすさ」docomo.ne.jp
- NTT-BPコラム 「Shinkansen Free Wi-Fi」を使う時の注意点ntt-bp.netntt-bp.net


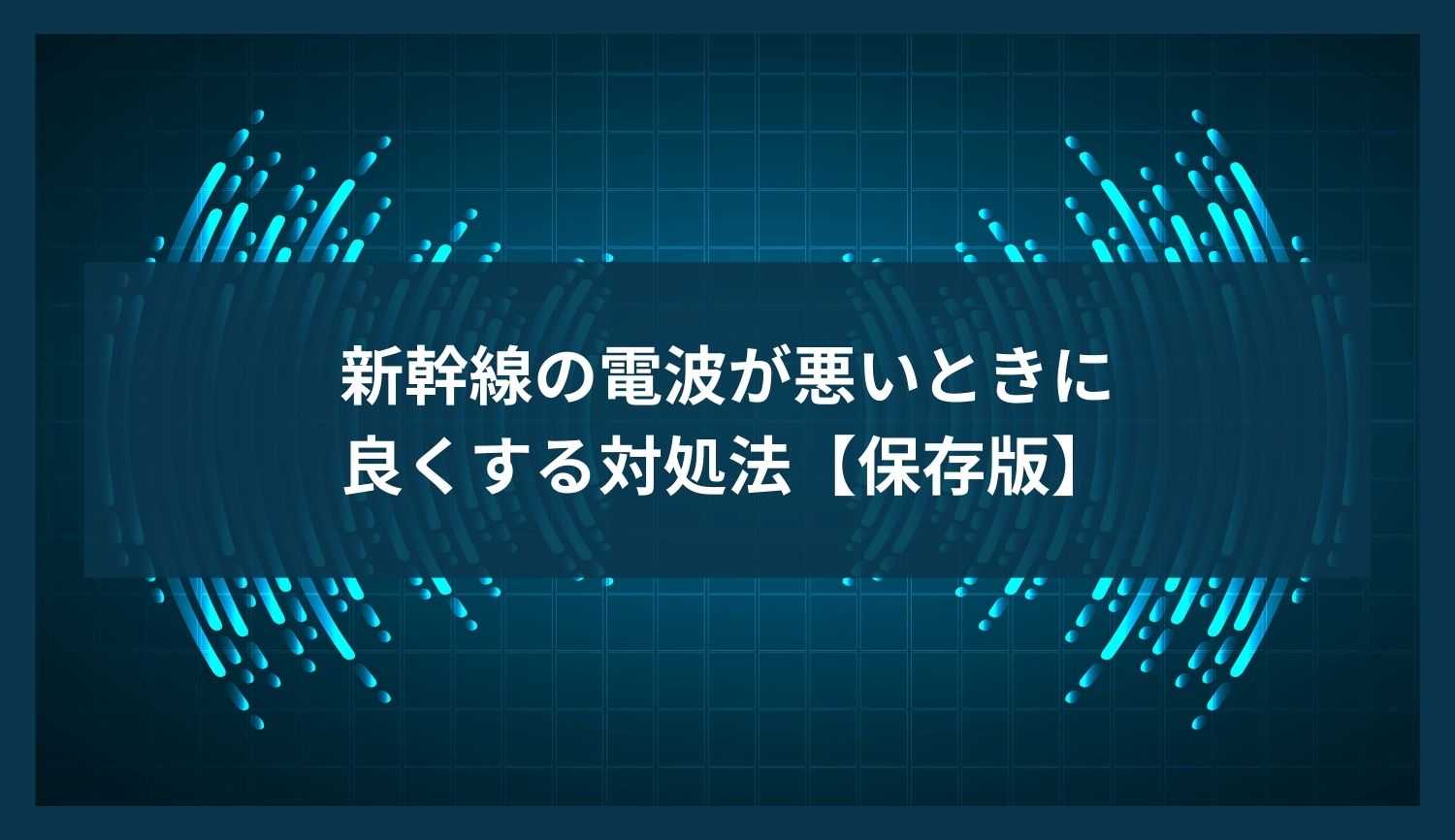



コメント