えきねっとはJR東日本が提供するインターネット上の指定券予約サービスです。自宅のPCやスマホから新幹線などの切符を予約できる便利な仕組みですが、その一方で、「使いにくい」との評価も根強く、ネット上でも度々話題になります。

多くの利用者がUIや操作性に不満を抱えており、イライラするポイントも少なくありません。本記事では、えきねっとが使いにくいとされる原因を解説し、UI/UX上の具体的な問題点やリニューアル予定について詳しく説明します。
えきねっとが使いにくいと評価されるのはなぜ?
えきねっとが一般利用者にとって使いづらいと感じられる主な原因は大きく3つあります。
これから順番に解説していきます。
原因1: 切符制度が複雑すぎて知識がないと迷う
まず、鉄道の切符の仕組み自体が非常に複雑であることが背景にあります。
JRには往復割引や乗継割引、都区内制度など昔から様々な料金制度があり、ネット予約ではJR各社ごとに販売ルールやシステムが異なるため、切符の買い方が一層わかりにくくなっています。そのため、きっぷの制度や予約方法を十分に理解していないと、自分の目的に合った最適な切符を選ぶのに戸惑ってしまうのです。
例えば、「乗継割引」一つとっても、その適用にはえきねっと上でチケット種別を「新幹線eチケット」から「紙のきっぷ」に切り替える必要があります。しかし、その操作方法が画面上では非常に分かりづらく、割引制度自体を知らない利用者がいます。
実際、乗継割引の欄がグレーアウト表示され「有効化する方法が見当たらない」状態では、多くの人はヘルプを読む前に「もういい!高速バスを探そう…」となりかねないと指摘する人もいます。
原因2: ユーザー目線に立っていないUI設計
次に、えきねっとのユーザインタフェースが直感的でなく、利用者視点に立っていないことも大きな問題です。
例えば、ログインページではパスワードを2度入力しなければいけないという謎の手間があり、他の会員登録サービスにはない仕様も珍しくありません。
どうやら、えきねっとの設計思想自体が「お客様の移動」ではなく「切符を売ること」を中心に据えている点も使い勝手を悪くしているようです。駅の窓口であれば、「○時頃に出発したい」と伝えれば係員が自動的に一番安い切符の組み合わせを提案してくれますが、えきねっとでは利用者自身が「どの切符をどう組み合わせるか」を選ばされる流れになっています。
画面上でも「この切符を買いますか?」「切符の種類は?」と次々に切符主体の質問が出てきて、利用者の関心である「どの経路でいくらかかるか」という視点とズレているわけです。このようにUI設計がユーザー目線から外れていることが、ストレスの原因になっています。
原因3: サービスの制約が多く利便性に欠ける
三つ目の原因は、えきねっとというサービス自体の利便性の制約です。
例えば、えきねっとで予約した切符は受取場所が限られており、JR東日本・北海道エリアの駅およびJR西日本北陸新幹線沿線の一部駅でしか発券できません。極端な例では、東海道新幹線の切符をえきねっとで予約すると東京近郊では受け取れても、復路を新大阪や広島で受け取ることはできないという制約があります。
また、毎日深夜にはシステムメンテナンスのため23:40~0:20および1:40~5:30の間は予約や変更手続きが一切できないという運用上の制限もあり、利用者にとって不便です。さらに、鉄道のネット予約システム全般に言える問題として外部サービスとの非連携があります。
航空券であれば旅行会社サイトなど外部からも予約でき、フライトとホテルをまとめて手配することも普通ですが、鉄道の指定券予約は各社が自社システム内に囲い込んでいるのが現状です。本来、多くの人が使う乗換案内アプリからシームレスに列車予約までできれば便利なはずですが、えきねっとを含め現状の鉄道予約はそれが叶っていません。
このようなクローズドなシステムゆえに、ユーザーは経路検索と予約購入を別々のサービスで二度手間で行わねばならず、結果的に「使いにくい」と評価されてしまうのです。
えきねっとのUI/UXでイライラするのはどうして?
以上の原因から、えきねっとのUI/UX上では具体的に次のような「イライラする」ポイントが指摘されています。
※ 指摘は外部メディアの論点を要約したものです。最新仕様は公式サイトをご確認ください。
| 項目 | 要旨 | 解説 | 参考 |
|---|---|---|---|
| ログイン時にIDが二種類あり混乱しやすい | 「ユーザーID」と「My JR-EAST ID」。 | ログイン画面にえきねっとユーザーIDとMy JR-EAST IDの入力欄が並び、どちらで登録したか忘れて戸惑う利用者が多い。普段使わない人ほど端末変更時の本人確認でつまずきやすい。 | toyokeizai.net |
| 経路検索結果から直接予約できず手順が煩雑 | 一覧→別画面選び直し。 | 出発地・目的地の検索後、表示された列車一覧からそのまま予約/空席確認へ遷移できず、別画面で再選択が必要。操作がシームレスでなく、何をすべきか直感的に分かりづらい。 | toyokeizai.net |
| 表示される料金情報が分かりにくい | 最安値ではない表示。 | 検索一覧の運賃・料金は紙のきっぷ通常期の額で、必ずしも現在の最安値ではない。最安経路の一目比較ができず、詳細ページへ進む手間が増え、提示価格と実際の支払額が乖離する場面がある。 | note.com |
| 割引の適用方法が直観的でない | 切替や操作が不明瞭。 | 乗継割引などの適用・切替がUI上わかりづらい例があり、操作方法が見当たらない/気づけない。結果として割引恩恵を受けられず、途中で予約を諦めるリスクも。 | note.com |
| 操作ステップが多くスマホでは見づらい | 遷移・入力が多段階。 | 経路検索→列車選択→きっぷ種別→料金確認…と画面遷移・入力項目が多く、スマホでは縦長スクロールになり見通しが悪い。入力変更で合計金額がリセットされ再入力が必要になる場面も指摘。 | note.com |
| サービス設計がユーザーの目的に合っていない | 「移動×費用」に直結せず。 | 「切符を買わせる」前提の画面設計になっており、利用者の本来の問い『A駅からB駅まで、いくらで行ける?』にスムーズに答えにくい。不要な確認が多く、近年のユーザー中心設計から逸脱しているとの声。 | note.com |
こうしたUI/UX上の不満点が積み重なり、「えきねっとは使いづらい」「イライラする」という評価につながっています。特に他の交通手段(高速バス予約サイトなど)と比べて操作が複雑なため、ユーザーの心理的ハードルが高くなってしまっているのです。
えきねっとはリニューアルされる予定があるのか?
JR東日本もこれらの課題を認識しており、えきねっとの改善に取り組んでいます。 実際、2021年6月27日にはサービス開始20年で最大規模となるサイトのリニューアルが行われ、予約操作のUIを大幅刷新するとともに、切符購入でJRE POINTが貯まる・使える機能などが導入されました。
このリニューアルによって、トップページから直接乗車区間や日時を入力して列車検索・申込ができるよう操作フローが改善されるなど、使い勝手向上が図られています。
また、リニューアル後は新機能としてJRE POINTを使った特典チケットやアップグレードサービスも開始され、利便性とおトクさの両面で強化がなされています。
さらに今後のリニューアル・機能拡充の予定も発表されています。JR東日本は2025年秋を目途に「えきねっと」をはじめとするチケッティングサービスの利便性向上策を打ち出しており、乗車日の3か月前から新幹線予約が可能になる早期予約サービスの開始や、列車の遅延・運休時にウェブ上で変更・払戻しができる機能の追加などを予定しています。
2025年9月頃には共通ID「JRE ID」とえきねっとが連携し、他のJR東日本グループサービスとシームレスに利用できるようになる予定です。これにより、すでにJRE IDを持っているユーザーはID・パスワード入力なしでログイン可能になるなど、面倒な複数ID問題も解消に向かう見込みです。
まとめ:デザインは大事
使いやすいデザインと優れたUXは、サービスの利用促進において極めて重要です。 幸いにも、JR東日本は大規模なシステム刷新や機能改善に取り組み始めています。今後、ユーザーの経験や専門家の知見を活かしながら、誰もがストレスなく使えるデザインへと進化していくことが期待されます。
鉄道利用者にとって分かりやすく快適な予約サイトになれば、利便性向上だけでなく鉄道離れの防止にも寄与するでしょう。ユーザー体験を設計するデザインの良し悪しがサービスの評価と信頼性を左右するということを、えきねっとの事例は改めて示していると言えます。
ユーザー視点に立った継続的な改善により、「使いやすいえきねっと」へと生まれ変わる日も近いかもしれません。


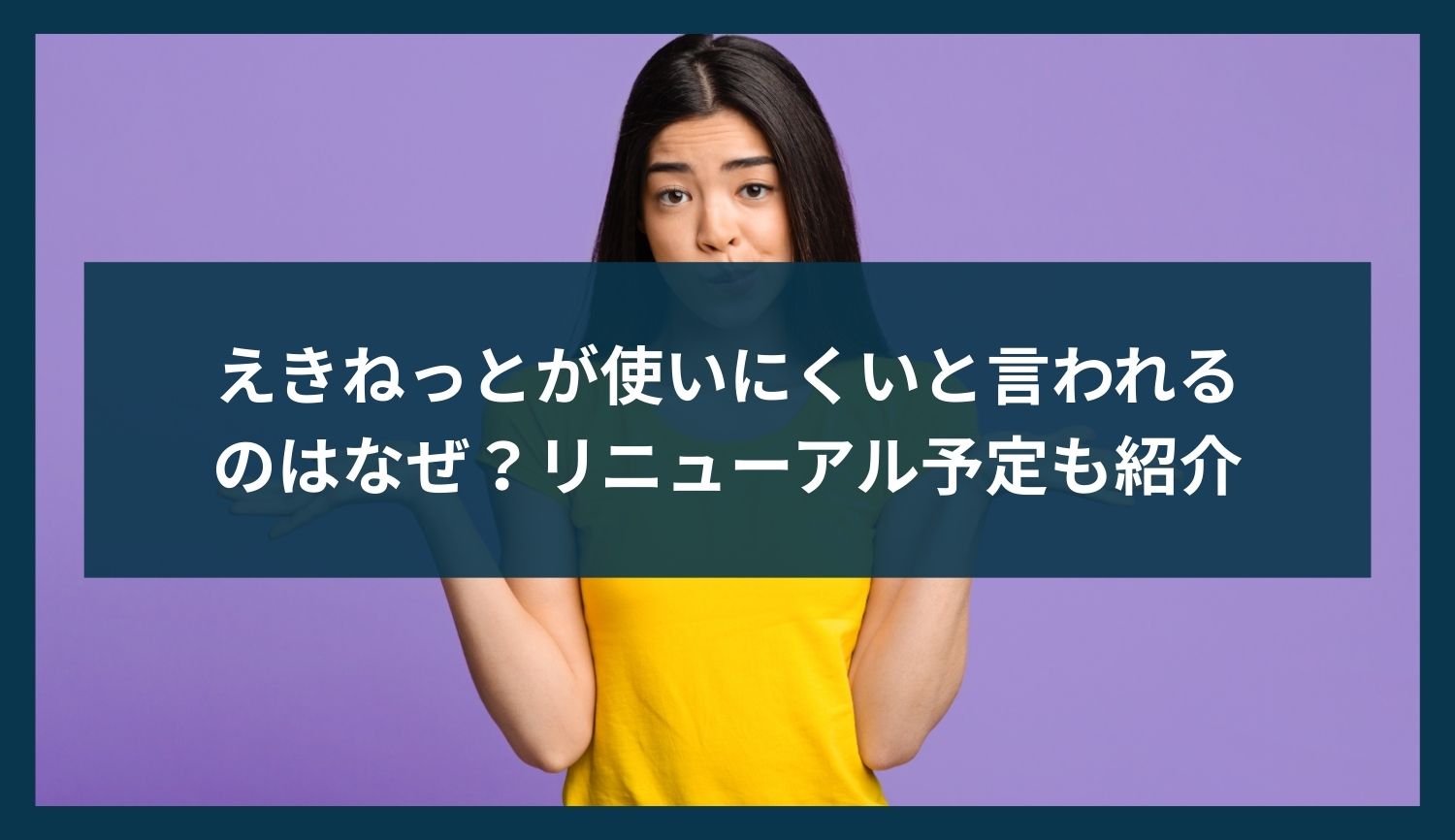
コメント