日本の鉄道では列車がお客様と接触する「人身事故」が頻繁に発生し、その度に列車は長時間ストップしてダイヤが乱れ、通勤・通学時間帯なら多くの人々が遅刻を強いられるなど社会的損失も甚大です。しかし、これだけ迷惑な人身事故が繰り返されているにもかかわらず、その発生数はなかなか減っていません。
実際、鉄道会社の統計では列車の人身事故による輸送障害(30分以上の遅延や運休)が2018年度には601件も報告されており、痛ましい事故がほぼ毎日どこかで起きている計算になります。なぜ人身事故はこれほどまでに減らないのか、本記事ではその理由をプロの視点から3つに整理して解説します。また、万一人身事故による遅延に遭遇した場合の対処法や、事故に起因して損害を被った際の対応策についても詳しく紹介します。
人身事故はマジで迷惑でしかないのに減らない理由
人身事故がもたらす影響の大きさを考えれば、発生件数を減らすことが重要ですが、現状では思うように減少していません。ここからは、人身事故が減らない主な理由を3つ説明します。
理由1:鉄道自殺が後を絶たず、抜本的な対策が困難
人身事故として報じられる事象の多くは、実際には列車への飛び込み自殺など故意によるものです。統計によれば、首都圏主要路線では過去10年で発生した人身事故の63%が「鉄道自殺」でした。

このように多数を占める自殺案件は、当事者が命を絶つ覚悟で行う行為であるため、その場で制止したり罰則で抑止したりすることが極めて難しいという問題があります。
全国的な自殺者数が減少傾向にある中で、鉄道における自殺は依然としてほぼ横ばいの水準に留まっています。
さらに、鉄道は確実に命を絶てる手段と認識されていることもあり、不幸にも追い詰められた人が最後の手段として選んでしまう傾向があります。そのため鉄道会社や行政も駅構内での巡回や監視カメラの増設、ポスター掲示といった自殺防止策を講じていますが、広大な路線網の中で全てのケースを事前に防ぐのは困難です。
理由2:ホームからの転落事故など不慮の人身事故が依然多い
人身事故には自殺以外にも、酔客や不注意によるホームからの転落、乗降中の列車との接触など不慮の事故も数多く含まれます。たとえば2013年度(平成25年度)には全国で発生した鉄道事故790件のうち、422件が人身事故でしたが、その内訳は約43%が自殺等(線路立ち入り含む)で、残る57%はホームからの転落・接触による事故でした。
スマートフォンに気を取られて足を踏み外したり、泥酔してホームから転落したりする例は後を絶ちません。また視覚障がい者の方が誤ってホームから落ちてしまう痛ましい事故も起きています。
本来防げるはずのこうした事故が無くならない背景には、安全設備の未整備と人的ミスの両面があります。ホームドア(可動式ホーム柵)は転落事故防止に極めて有効ですが、現在でも未設置の駅が多数あります。
2002〜2009年度の8年間で全国約9,000件の人身事故が発生しましたが、その約半数弱は駅構内で起きており、そのうち自殺以外の転落・接触事故が約3分の1を占めました。そして驚くべきことに、この転落・接触事故の約半数は酔っ払った乗客によるものだったのです。
ホームドアさえあれば防げた命も多いと指摘されています。統計上も、ホームドア設置駅では本来起こり得る転落事故が8年間で約190件発生するはずのところ、実際には12件しか発生しなかったというデータがあります。つまりホームドアがあれば大半の転落・接触事故は防止できるのです。
しかし地方の駅や利用客の少ない路線を中心に、ホームドアの普及はまだ十分とは言えません。2012年時点でホームドアが設置された駅は全国で539駅、全駅のわずか5%程度に過ぎませんでした。首都圏では山手線や主要私鉄などで急速に整備が進んでいるものの、全ての駅で乗降時の安全が確保されるまでには時間がかかるでしょう。
理由3:法的・制度的な抑止力が弱く、事故をゼロにできない
人身事故が後を絶たないもう一つの理由は、事故を起こした本人や遺族に対する法的な責任追及が現実には限定的で、十分な抑止力になりにくい点です。例えば列車を止めるような人身事故を起こせば「多額の損害賠償を請求される」という話を耳にしたことがあるかもしれません。
確かに鉄道会社は、振替輸送に要した費用や乗務員の人件費、車両の修理代など損害を算出し、朝のラッシュ時のターミナル駅で長時間運休ともなれば賠償額が億単位に達する可能性もあるとされています。
しかし実際のところ、そうした巨額の損害賠償が満額支払われるケースは多くありません。事故当事者が死亡した場合、賠償請求は遺族(相続人)が引き継ぐ形になりますが、すべての事故で賠償金が請求されるわけではなく、請求する場合でも鉄道会社と遺族側で協議して現実的な和解金額を探るのが一般的です。
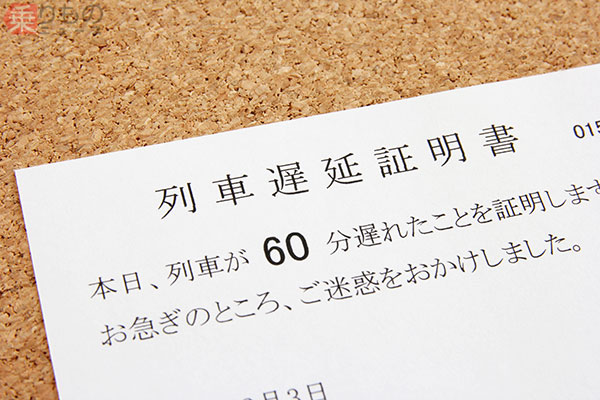
さらに遺族の側が経済的負担に耐えられない場合、相続放棄という手段で法律上の支払い義務を免れることも可能です。そのため、たとえ鉄道会社が損害賠償を請求したとしても全額が支払われる例は少なく、結局のところ事故による損失の多くは鉄道会社が泣き寝入りせざるを得ないのが現状です。
人身事故で遅延したら何をしたらいい?
次に、もしも自分が乗っている電車が人身事故に遭遇して遅延してしまった場合に取るべき対処法を解説します。突然の足止めに焦ってしまいがちですが、以下の3つのポイントを押さえて行動すれば、被害を最小限に抑えることができます。
その1:振替輸送など代替ルートを活用する
人身事故発生直後は、まず鉄道会社から運行見合わせや復旧見込み時間についてアナウンスがあります。その際、「振替輸送」の案内があれば積極的に利用しましょう。
振替輸送とは、すでにお持ちの乗車券区間で輸送障害が発生した場合、指定された他の鉄道会社等の経路により、迂回して目的地までご利用いただける仕組みです。例えばJR線が止まった際に私鉄や地下鉄への振替輸送が行われれば、改札で振替乗車票を受け取るか係員に申し出ることで、その路線を追加運賃なしで利用できます。
振替輸送が提供されていない場合でも、自力で他の路線や交通手段に切り替えた方が早く目的地に着けることもあります。スマートフォンの乗換案内アプリや鉄道会社の公式サイトで運行情報を確認し、復旧見込み時間と迂回経路の所要時間を比較しましょう。
もし振替輸送指定外の経路にやむを得ず乗車した場合、かかった追加運賃については勤務先に事情を説明すれば通勤手当の支給対象になることもあります(会社の規定によります)。いずれにせよ、「待つか迂回するか」早めに判断し行動に移すことが肝心です。
その2:遅延証明書を取得する
列車遅延により学校や職場に遅刻しそうな場合、まずは電話やメールで状況を報告しましょう。同時に、鉄道会社が発行する「遅延証明書」を入手しておくことをおすすめします。
遅延証明書とは、その列車が何分遅れたかを示す証明書で、駅の窓口で紙でもらえるほか、後で鉄道会社のサイトからPDFをダウンロードすることもできます。多くの鉄道会社では5分以上の遅延が発生すると遅延証明書を発行する仕組みになっており、JR東日本などではホームページ上で当日の遅延証明を時間帯別に公開しています。
証明書があれば遅刻やキャンセルの正当な理由を客観的に示せるため、学校や勤務先への報告時に提出を求められても安心です。特に就業規則で遅延証明書の提出が定められている企業もありますので、事故による遅刻の際には忘れず入手しておきましょう。
証明書をもらうタイミングがないほど急ぐ場合は、後日でも鉄道会社サイトから発行期間内であれば取得可能です。連絡と証明によって、「人身事故で電車が止まった」という自分では避けようのない理由であることを誠実に伝えることが大切です。
その3:落ち着いて安全を確保し、必要なら旅行を取り止める判断も
人身事故発生時には混乱しがちですが、何より自身の安全を最優先に行動してください。プラットホームや車内が混雑していても押し合ったり無理に移動したりせず、駅係員や乗務員の指示に従いましょう。絶対に勝手に線路上に降りたり、遮断機の下りた踏切に立ち入ったりしてはいけません。
救助や現場検証のため列車の停止が長引くこともありますが、焦って非常ドアコックを扱うような行為は二次被害を招く危険があります。鉄道会社は一刻も早い運転再開に努めていますので、利用者側も冷静に協力する姿勢が大切です。
もし人身事故によって著しい遅延が発生し、目的の用件に間に合わなくなってしまった場合、思い切ってその日の旅行(乗車)を中止する判断も必要です。鉄道会社の旅客営業規則では、事故や運休で列車が運転できなくなった場合、切符代の払い戻しなどの措置を定めています。
途中で旅行を取り止める場合は乗車券の残区間の運賃が返金され、特急券なども全額払い戻しされます。たとえば出張先への到着が不可能になった場合などは無理に向かわず引き返して、後日改める方が結果的に得策です。この際、駅係員に申し出れば払い戻し手続きを案内してくれるでしょう。
人身事故で損害が発生したらどうすればよい?
最後に、人身事故によって生じた損害への対処について説明します。ここでいう損害とは大きく分けて二つのケースがあります。(1)事故の影響で自分が金銭的・物理的な被害を被った場合と、(2)事故そのものを起こした(または家族が起こした)ことによって鉄道会社等から損害賠償を請求された場合です。それぞれ対応が異なりますので順に見ていきましょう。
まず事故による利用者側の損害についてです。例えば人身事故のせいで新幹線に乗り継げず予約していた飛行機に乗れなかった、タクシー代が余計にかかった、といったケースが考えられます。この場合、残念ながら鉄道会社に補償を求めることはできません。
なぜなら人身事故は鉄道会社に過失のない不可抗力の事象であり、運送約款でも「定められた範囲以上の対応はいたしません」と明記されているからです。鉄道会社が提供するのは先述の運賃の払い戻しや振替輸送など決められたサービスに限られ、それ以上の第三者への損害(例えばビジネス上の損失や宿泊費など)は自己負担となってしまいます。
悔しい気持ちになるかもしれませんが、法律上は「不可抗力による遅延」として賠償責任が問われないため、利用者側で旅行保険に加入していない限り金銭補償は望めないのです。
次に(2)の、自分や家族が事故を起こしてしまい鉄道会社から損害賠償を請求されたケースについてです。この場合は、まず落ち着いて請求内容を確認し、可能であれば弁護士など専門家に相談することをお勧めします。前述のとおり、鉄道会社から請求される損害賠償額は発生状況によっては非常に高額になる可能性があります。
しかし実際には全額を支払わずに当事者側と鉄道会社との協議で和解となる事例も多く、遺族であれば相続放棄という手段で請求を免れることも可能です。請求書が届いたからといって直ちに全額を支払わなければならないわけではありません。
万一、事故を起こしてしまった本人が生存している場合は、鉄道営業法違反や業務上過失致死傷など法的責任も含めて対処が必要になるため、警察や弁護士の指示に従ってください。死亡事故で遺族に請求が来た場合には、支払い能力や過失の程度を踏まえ鉄道会社と話し合いを持つことになります。
鉄道会社側も現実的な落としどころを探る姿勢が一般的で、初回から法外な満額を要求されることは考えにくいようです。いずれにせよ深刻な局面ですので、決して一人で抱え込まず周囲や専門家の力を借りて対応策を検討しましょう。
まとめ
人身事故は利用者にとって「マジで迷惑」であり、遅延や運休という形で日常生活に支障をきたす問題です。しかし、その背景には社会の抱える課題やインフラ整備上の制約が存在し、簡単には減らせない現状があります。
鉄道各社もホームドアの設置拡大や列車見張員の配置、異常時対応の訓練強化など、事故削減に向けた努力を続けています。今後、こうした安全対策がより広く行き渡り、社会全体で自殺予防やマナー向上に取り組むことで人身事故ゼロへの道筋が開けていくことが期待されます。
我々利用者も人身事故はいつどこで遭遇するか分からないものと肝に銘じ、日頃から余裕を持った行動や情報収集を心がけることも大切です。そして万一巻き込まれてしまった際には、この記事で述べたように落ち着いて適切に対処し、被害を最小限に留めるようにしましょう。


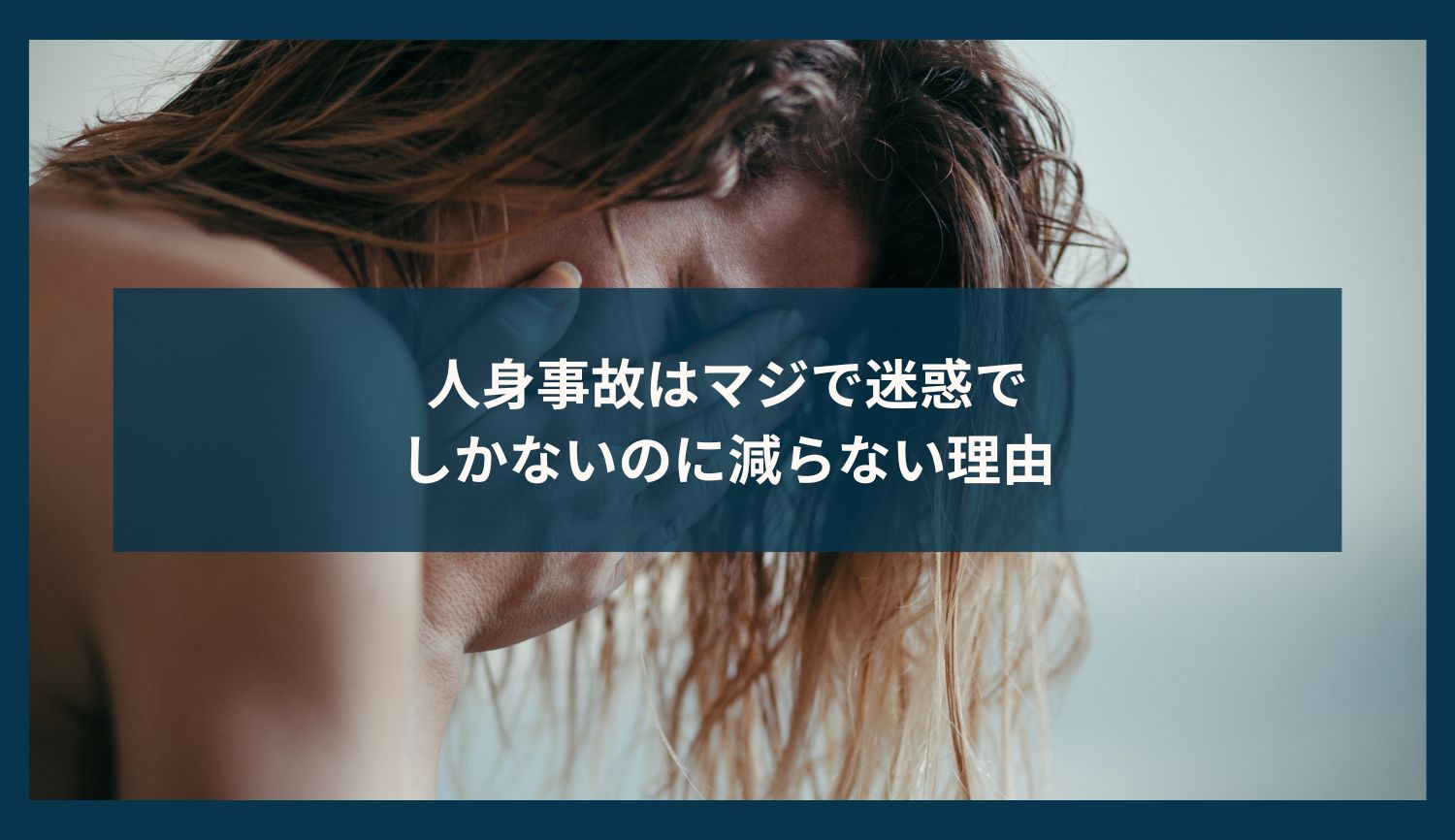
コメント