モバイルSuicaとモバイルPASMOはいずれもスマートフォンで利用できる交通系ICカードサービスです。電車やバスの乗車、駅ナカやコンビニでの支払いまで、キャッシュレスに生活を支えるインフラであると言えます。
首都圏ではJR東日本が発行するSuicaと、私鉄・地下鉄事業者が参加するPASMOの2種類が広く普及しており、それぞれモバイル版も提供されています。では、「両方のモバイルICカードをスマホに入れて併用したら便利では?」と考える方もいるでしょう。
本記事では、モバイルSuicaとモバイルPASMOを併用することは可能なのか、またそのメリット・デメリットを詳しく解説します。
モバイルSuicaとモバイルPASMOの併用はあり?
結論から言えば、モバイルSuicaとモバイルPASMOを1台のスマホで併用すること自体は可能です。例えば、iPhoneのWalletアプリではSuicaとPASMOの両方のカードを登録・管理でき、Androidでもおサイフケータイ対応端末で2021年以降この併用が正式にサポートされました。
ただし、併用する場合は注意が必要です。スマホに複数の交通系ICカードを入れていても、改札機などにタッチして使えるのは「メインカード」に設定した1枚のみとなります。利用時に状況に応じて自動でSuicaとPASMOが切り替わってくれるわけではなく、必要に応じて手動でメインに使うカードを切り替える操作が求められます。
とりわけ、両方のカードにそれぞれ定期券を搭載しているようなケースでは、JR東日本も「意図しないカードで運賃が引き去られるおそれがあるので、このような使い方は避けてください」と公式に注意喚起しています。要するに、「併用はできるが、誰にでも強く推奨できる使い方ではない」というのが現状です。
モバイルSuicaとモバイルPASMOを使い分けるメリット
モバイルSuicaとモバイルPASMOの併用には慎重な運用が求められますが、上手く使い分ければ利点もあります。ここから、モバイルSuicaとモバイルPASMOを使い分ける3つのメリットについて説明します。
メリット1:JR・私鉄それぞれのポイント特典を最大限に活用できる
モバイルSuicaとモバイルPASMOを併用する最大のメリットの一つは、JR系と私鉄系それぞれのポイントサービスを漏れなく享受できる点です。JR東日本のエリアではSuica利用によりJRE POINTが貯まりますが、モバイルSuicaなら紙のSuicaカードよりもポイント還元率が大幅に高く設定されています。
具体的には、改札利用時のポイント付与率がカード型Suicaの0.5%(200円で1ポイント)に対し、スマホ版Suicaでは2%(50円で1ポイント)と4倍も優遇されています。定期券購入やグリーン車利用でも同様にポイントが付き、モバイルSuica利用者はJRでの“乗るだけポイ活”がよりおトクになります。
一方、私鉄・地下鉄エリアではPASMO側のポイントサービスがあります。たとえば、東京メトロでは、PASMOを所定の「メトロポイントクラブ」に登録して乗車すると運賃に応じてメトロ独自のポイントが貯まります。
メトポは貯まったポイントをPASMO残高にチャージして運賃や買い物に利用可能なプログラムで、10ポイント=10円としてPASMOにチャージできます。このメトポは東京メトロ線内の乗車が対象ですが、PASMOを活用することで地下鉄利用でもポイント還元が受けられるわけです。さらにPASMO加盟の私鉄各社でも、東京メトロ以外に独自の乗車ポイントや特典を用意している場合があります。
メリット2:両カードの独自サービス・機能を使い分けられる
SuicaとPASMOは基本的な機能や使えるエリアこそ共通化されていますが、提供元が異なるため独自のサービスや機能の違いがあります。2つを併用すれば、Suicaでしか使えないサービスとPASMOでしか使えないサービスの両方を享受できるのもメリットです。
例えばモバイルSuicaならではの機能として、JR東日本の駅のグリーン車(自由席)を利用する際にスマホ上で事前に「Suicaグリーン券」を購入できますが、モバイルSuica経由だと車内購入より割安な「モバイルグリーン料金」が適用されます。
また、新幹線の電子チケットサービス(「タッチでGo!新幹線」や「モバイル特急券」等)にも対応しており、改札入場だけで新幹線に乗車することも可能です。さらにモバイルSuicaはJRE POINTとの連携がスムーズで、日常の電車利用や買い物でJRE POINTを自動的に貯める設定もできます。
一方のモバイルPASMO独自のメリットとしては、アプリ上で私鉄・地下鉄の電車定期券や路線バスの定期券を購入できる点が挙げられます。モバイルSuicaではバス定期券をアプリ購入できず窓口対応が必要でしたが、PASMOならスマホでバス定期も完結します。
また、バス乗車に応じて貯まる「バス特(バス利用特典サービス)」のポイント残高もアプリから確認でき、紙の回数券的なバスポイントを管理しやすい利点もあります。
メリット3:複数の定期券をスマホ1台に収めて持ち歩ける
通勤・通学経路によっては、鉄道(JR)とバス、あるいはJRと私鉄など複数の会社の定期券が必要になる場合があります。通常、JR線の定期券はSuica系でしか発行できず、私鉄やバスの定期券はPASMOでしか発行できませんe。
そのため、紙のICカード時代であればSuica定期とPASMO定期を2枚持ち歩いたりして対応していたケースでも、モバイルSuicaとモバイルPASMOを両方導入すればスマホ1台で2種類の定期券を携行できるようになります。
具体的には、「JR区間の定期はモバイルSuica、バス定期はモバイルPASMOで購入する」といった使い分けをすれば、スマホだけで電車もバスも定期利用できて身軽です。複数のカードを財布に入れて改札で混在させる心配もなくなります。
また、用途別にカードを使い分けられることから、経費精算や家計管理の面でもメリットがあります。仕事用の移動はモバイルPASMO、プライベートの移動はモバイルSuicaといった具合に使うカードを分けておけば、それぞれの利用履歴を明確に区別できるため精算や記録がしやすくなります。
モバイルSuicaとモバイルPASMOを使い分けるデメリット
一方で、モバイルSuicaとモバイルPASMOを併用するときには注意すべきデメリットやリスクも存在します。続いて、併用運用する際に生じうる3つのデメリットについて解説します。
デメリット1:メインカード切替えの手間(自動での切替え不可)
前述のように、スマートフォン上でSuicaとPASMOを2枚同時に設定していても改札機にタッチして使われるのは「メインカード」に指定された1枚のみです。つまり、利用するシーンに応じて自分で都度メインカードの設定を切り替えなければなりません。
iPhoneの場合はWalletアプリの「エクスプレスカード」設定で優先するカードを選べますが、電車に乗る前に設定変更する手間が発生します。Androidでもおサイフケータイアプリ等でメインカードの切替操作が必要です。
この手動でのカード切替えは、併用運用の煩雑さとして無視できません。一枚のカードで済ませている場合には何も意識せず改札を通れますが、併用していると「今日はどちらを使うか」を逐一考えて設定する必要があります。特に朝夕の慌ただしい時間帯に切替えを失念すると後述するトラブルにも繋がるため、運用管理の負担は確実に増えるでしょう。
デメリット2:切替え忘れによる定期券未適用・誤課金のリスク
メインカードの切替え運用には、ユーザーのヒューマンエラーによる思わぬ課金リスクも伴います。
例えば、モバイルPASMO側に私鉄の定期券区間を持っているのに、スマホのメインカード設定を誤ってモバイルSuicaのまま改札にタッチしてしまったとしましょう。この場合、本来定期で無料で通れる区間であってもSuica側のSFから運賃が引かれてしまいます。
JR東日本は「Suica/PASMO双方に定期券を持ち、都度メインカードを変更しながら利用することはおやめください。誤って意図しないカードでSF引き去りとなる恐れがあります」と注意を呼びかけています。一度ミスをすると二重払いになったり、後から払い戻しや精算の手間がかかったりする可能性もあり、カード切替え忘れは利用者にとって大きなリスクです。
また、一つの経路を乗車中に2枚のカードをまたいで使うこともできません。定期券区間を越えて乗り越した際、その延長料金だけ別のカードで精算するといった芸当は不可能で、乗車の際にタッチした1枚のICカードで全行程を完結させる必要があります。
したがって、切替えのタイミングを間違えると、本来定期でカバーできた区間外乗車の扱いなどもスムーズにいかなくなるでしょう。
デメリット3:残高・定期券情報の移行不可で管理が分散する
モバイルSuicaとモバイルPASMOは相互利用で似たように使えるとはいえ、システム上は別組織が運営する別サービスです。そのため、両者の間でチャージ残高や定期券情報を融通することはできません。
具体例を挙げると、モバイルSuicaに入っている1,000円をモバイルPASMOに移し替える、あるいはSuicaの定期券をそのままPASMO側に切り替える、といったことはシステム上不可能です。
もし「やはり一つにまとめたい」と感じてどちらかを解約する場合、残高や定期券は基本的に払い戻して改めてもう一方で買い直す必要があります。払い戻しには所定の手数料が差し引かれるため、二枚に資金を分散していると無駄なコストが発生する可能性もあります。
また、単純に残高や履歴の管理が2つに分かれる煩雑さもデメリットです。SuicaとPASMOでそれぞれチャージ残高を管理し、オートチャージ設定も別々に行い、それぞれ利用明細を確認するといった具合に、一本化している場合と比べて管理すべき項目が増えます。
どちらか一方にまとめておけば、「残高不足になっていないか」「有効期限切れの定期券はないか」といったチェックもワンストップで済みますが、併用時は両方について気を配らなければなりません。特に残高面では、少額ずつ両カードに余りが出て無駄になりがちという声もあります。こうした資金や情報管理の煩雑化**は、モバイルSuica/PASMOを併用する上で避けて通れないデメリットと言えるでしょう。
まとめ:交通系ICカードは統一した方が無難
モバイルSuicaとモバイルPASMOを併用するメリット・デメリットを見てきました。ポイントサービスの二重取りや各種機能のフル活用など、併用には確かに魅力的な利点があります。
一方で、運用上の手間増加やミスによるリスク、そしてシステム上の非融通性といったデメリットも看過できません。特に定期券を絡めた使い分けは公式からも非推奨とされるほど注意が必要であり、一般ユーザーにとってハードルが高い面があります。
総合的に見ると、よほどの上級者や特別な事情がない限り、交通系ICカードはモバイルSuicaかモバイルPASMOのどちらか一方に統一して利用するのが無難でしょう。実際、首都圏での利用シーンであればSuicaでもPASMOでも大差なく使えるため、ポイント重視ならSuica、生活圏が私鉄中心ならPASMOというように自分に合ったメインカードを1枚選ぶのが安心な選択です。
もちろん併用自体は可能なので、この記事で挙げたメリットに魅力を感じ管理も徹底できる方はチャレンジしてみる価値があります。しかし、多くの利用者にとっては**「カードを一本化してシンプルに使う」方がトラブルもなく安心できるでしょう。交通系ICカードは生活の基盤となる便利なツールだけに、確実でストレスの少ない運用方法を選ぶことをおすすめします。
参考資料・出典:
- JR東日本 「モバイルSuica」公式FAQmsfaq.mobilesuica.comsupport.mobile.pasmo.jp
- 東京メトロ ニュースリリース(メトロポイントサービス)tokyometro.jp
- Impress Watchほか メディア報道・専門サイトwatch.impress.co.jpd-money.jpd-money.jp
- 有識者ブログ「The Goal」 他matsunosuke.jpaucfan.com


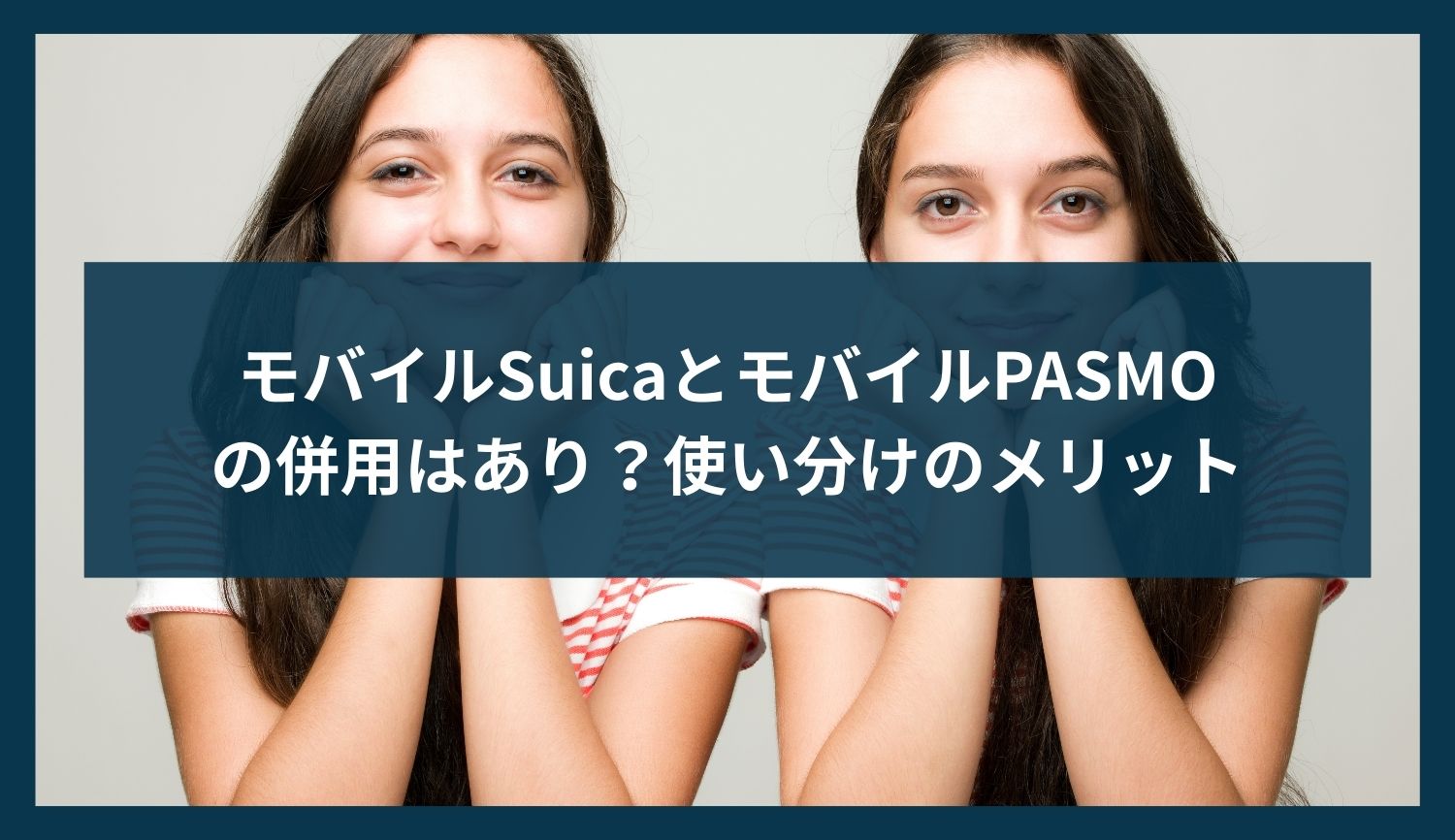
コメント