多くのビジネスパーソンが経験する朝の通勤電車での居眠りは睡眠不足を補う手段として考える人も多いですが、実は朝の電車での睡眠には様々なリスクが潜んでいることをご存知でしょうか?
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の三島和夫部長は、通勤電車での睡眠について「朝の出社時の通勤電車で眠ることは睡眠不足を補えるとして推奨される一方で、注意すべき点もある」と指摘しています。

本記事では、朝の電車で眠ることによる具体的なリスクと、それらを避けるための効果的な眠気防止対策について、医学的根拠に基づいて詳しく解説します。通勤中の睡眠習慣を見直し、より安全で健康的な通勤を実現するための参考にしてください。
朝の電車で寝ない方がいいと言われる4つの理由
朝の通勤電車での睡眠が推奨されない理由は、健康面から安全面まで多岐にわたります。
これから4つの主要な理由について詳しく説明します。
理由1:首や肩への身体的負担が大きい
第1に、電車内での不適切な姿勢での睡眠は、首や肩の筋肉に深刻な負担をかけ、慢性的な痛みの原因となります。
All Aboutの肩こり専門記事によると、「電車の居眠りで首や肩周りを痛める方は多い」とされており、特に20分以上うつむいたまま動かずに熟睡した場合、頸部を支える組織に問題が起き、回復までに40分以上かかると報告されています。人間の頭部は約5kgの重量があり、うつむき姿勢になることで首の後側筋肉が伸張され、大きな負荷がかかります。座り姿勢では背骨のS字カーブが維持しにくく、腰部への負荷が増加し、その影響が頸部にまで及ぶことが医学的に証明されています。

具体的なリスク:電車内での居眠りによる首の痛みには以下の4つのパターンが報告されています3:
- うつむき姿勢による筋肉の緊張:頭部が下がり、首の後ろ側から肩にかけて張りが残る
- 背中全体の負担:背中の中央付近からうなだれる姿勢により、首だけでなく背中全体に違和感が生じる
- 急激な頭部の動き:寝過ごしに気づいて慌てて起き上がる際の「ぎっくり首」
- 天井方向への過度な伸展:首の関節に負担をかけ、気分が悪くなるケースもある
理由2:防犯上のリスクが高まる
第2に、電車内での睡眠は置き引きなどの犯罪に遭うリスクを大幅に高めます。警察庁の統計によると、令和5年の置き引き認知件数は10,346件で、前年より1,038件増加しており、1日あたり約28.3件の置き引きが認知されています。電車内での置き引きは代表的な手口の一つとして挙げられています。
ALSOK(綜合警備保障株式会社)の防犯情報によると、電車内での置き引きの典型例として「電車で居眠りしている所有者の隙を見計らい、網棚に載せてあるカバンや上着などから荷物を持ち去る」ケースが報告されています。

置き引きは窃盗罪または占有離脱物横領罪に該当し、窃盗罪の場合は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる重罪です。被害者になるだけでなく、気づかずに持ち物を放置することで、周囲の乗客にも不安を与える可能性があります。
理由3:乗り過ごしによる遅刻リスク
第3に、電車内での睡眠は目的駅での降車を妨げ、重大な遅刻や業務への支障を引き起こします。
乗りものニュースが実施したアンケート調査(857人回答)では、82.5%の人が通勤・通学帰りの列車で寝過ごした経験があると回答しています。また、寝過ごしの距離については、約6割の人が降りようと思っていた駅から30分以内で気づいているものの、7.4%の人は121分以上も寝過ごしており、深刻な影響を与えるケースも存在します。

東京睡眠医学センターの遠藤拓郎院長によると、電車内で目的の駅に到着したことに気づけるのは「眠りが浅いから」であり、深い眠りモードに入ると寝過ごしてしまいます。朝の疲労が蓄積した状態では、予想以上に深い眠りに入るリスクが高くなります。

理由4:夜の睡眠の質への悪影響
第4に、朝の電車での睡眠は、本来必要な夜間の質の高い睡眠を阻害する可能性があります。国立精神・神経医療研究センターの三島和夫部長は、「同じ20分眠る場合でも、時間帯が早ければ早いほど、夜のメジャースリープへの影響が少なく、徐波睡眠を減らさない」と述べており、朝の仮眠でも夜の睡眠に影響する可能性があることを示唆しています。
人間の睡眠は徐波睡眠(深い眠り)と浅睡眠の両方が必要であり、「大切なのは、最初に徐波睡眠が出て後半は浅くなっていく、メジャースリープ(まとまった睡眠)全体の構造を崩さないこと」です18。朝の電車での不規則な睡眠は、この自然な睡眠構造を乱す可能性があります。
三島部長によると、「体にはサーカディアンリズムと呼ばれる周期があり、血圧であれホルモンであれ自律神経であれ、24時間周期のメカニズムで動いています」。不規則な睡眠パターンは、この重要な生体リズムを乱し、長期的な健康への悪影響をもたらすかもしれないのです。
朝の電車で眠気を防止する対策
電車内での睡眠を避けるためには、根本的な睡眠不足の解消と、通勤中の覚醒維持が重要です。これから3つの効果的な対策について説明します。
その1:十分な夜間睡眠の確保
朝の電車での眠気を防ぐ最も効果的な方法は、夜間に質の高い十分な睡眠を確保することです。医師監修のNELLの睡眠情報によると、「一般的に日本人の成人の平均睡眠時間は6時間~8時間」とされており、全米睡眠財団では就労世代に7~9時間の睡眠を推奨しています。
睡眠の質向上方法:
- 規則正しい生活リズム:体内時計を整えることで、自然な睡眠と覚醒のサイクルを維持
- 就寝前のリラックス:スマホやパソコンの使用を控え、リラックスできる行動を取り入れる
- 適切な睡眠環境:寝室の温度・湿度、照明の明るさ、寝具の質にこだわる
広島大学大学院の林光緒教授は、「マイクロスリープや日中の眠気を防ぐためには、睡眠不足を解消することが第一になります。10分でも15分でも、可能な限り睡眠時間を伸ばすように努めてください」と強調しています。
その2:カフェインの戦略的摂取
カフェインは適切に使用することで、効果的な覚醒効果を得ることができます。睡眠専門医の遠藤拓郎先生によると、「カフェインの効果が表れるのは、口に入ってから20~30分後」であり、通勤前にコーヒーを飲むことで、電車内での覚醒状態を維持できます。
長距離ドライバー108名を対象とした調査では、「コーヒーを飲む」ことが有効な眠気対策として挙げられており、プロの運転者も実践している方法です。ただし、カフェインには個人差があり、摂取しすぎると夜の睡眠に悪影響を与える可能性があるため、適量を心がける必要があります。

その3:物理的な覚醒維持方法
電車内でできる物理的な眠気対策を実践することで、睡眠を防ぐことができます。長距離ドライバーの眠気対策研究によると、「人は上がった体温が下がるときに眠くなるため、眠気防止には体温を上げないことが何より大切」です。電車内では上着を脱ぐ、窓際の場合は適度に換気するなどの体温管理が有効です。
姿勢の維持:
- 背筋を伸ばした状態を維持する
- 定期的に肩や首を軽く動かす
- 足の位置を変えるなど、軽い動きを取り入れる
意識的な活動:
- 読書や資格勉強など、頭を使う活動
- スマートフォンで有益な情報収集
- 音楽や音声コンテンツの聴取
まとめ:事故が起きる可能性がある
朝の電車での睡眠は、一見すると睡眠不足を補う手段として有効に思えますが、実際には身体への負担、防犯リスク、乗り過ごしの危険、そして睡眠の質への悪影響という4つの重大な問題を抱えています。
特に深刻なのは、睡眠不足が慢性化することで発生するマイクロスリープの危険性です。広島大学の研究によると、マイクロスリープは「いつ生じるか予想できず、突然意識が途切れるため非常に危険であり、そういったリスクが生じるほど睡眠が足りていないと認識する必要があります」。
実際に、JR東日本では2025年5月に高崎線で運転士が走行中に居眠りをする事故が発生しており、同様に横浜線でも運転士の居眠りにより停車位置を誤るトラブルが報告されています。これらの事例は、睡眠不足による注意力の低下が重大な事故につながる可能性を示しています。
通勤時の安全と健康を確保するためには、夜間の十分な睡眠確保を最優先とし、朝の電車内では覚醒状態を維持することが重要です。一時的な睡眠不足の解消よりも、根本的な生活リズムの改善と睡眠の質向上に取り組むことで、より安全で健康的な通勤生活を実現できるでしょう。
個人の安全だけでなく、公共交通機関を利用する全ての人の安全を守るためにも、朝の電車での睡眠は避け、適切な眠気対策を実践することを強く推奨します。


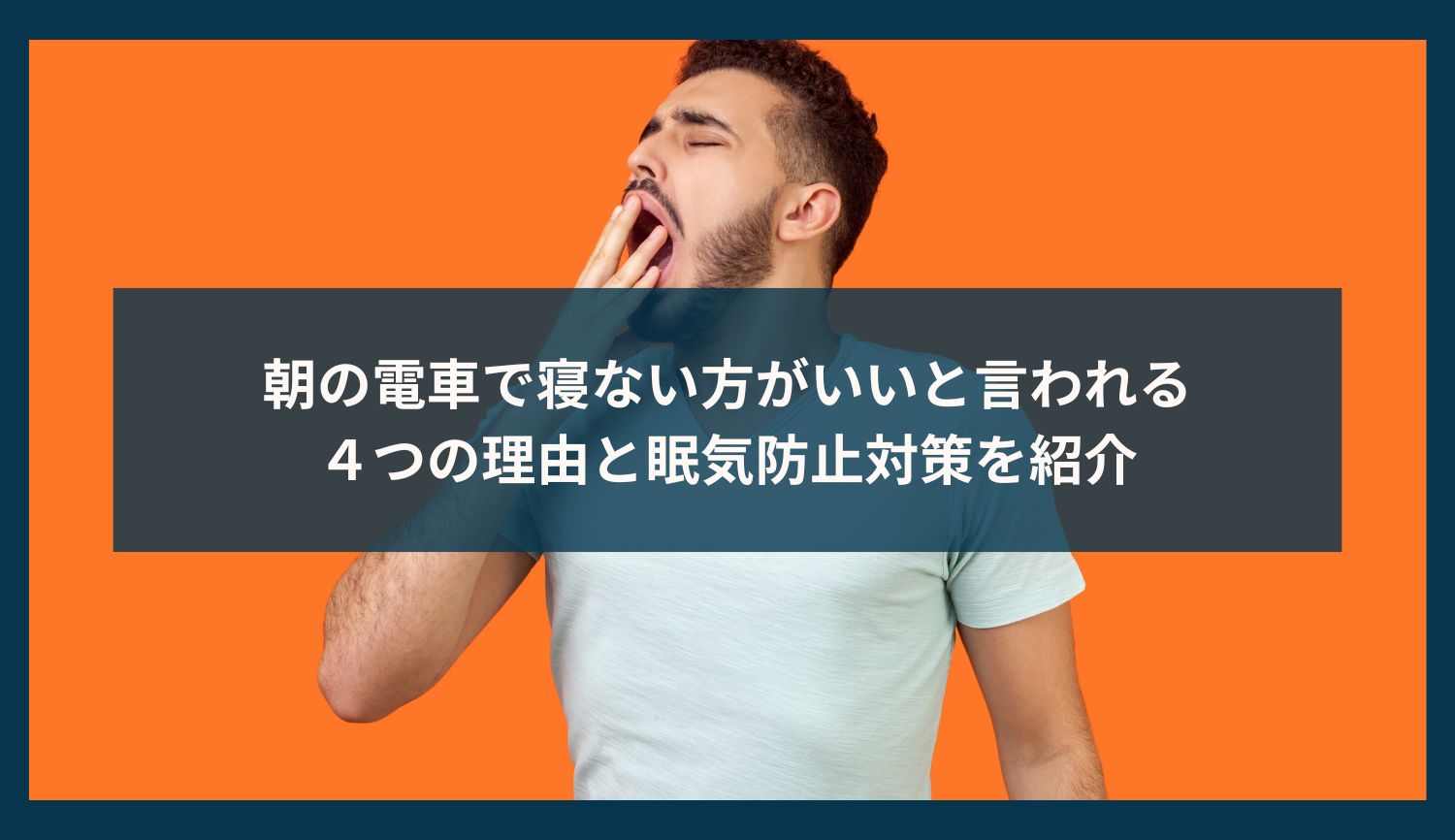

コメント