磁気定期券とは、券面裏の黒い磁気ストライプに通勤・通学定期の情報を記録した乗車券のことです。ICカード定期券が登場する以前から発行されている従来型の定期券で、改札機では投入して利用します。
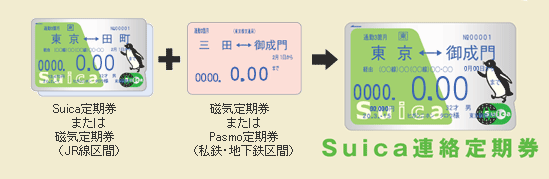
券面には利用できる区間や有効期限が印字されており、紙の定期券と比べて自動改札に対応している点が特徴です。現在、多くの鉄道事業者でIC定期券が主流となっていますが、一部では2025年まで磁気定期券の発売が続けられており、引き続き利用する乗客もいます。
本記事では磁気定期券の基本的な使い方から、そのメリット・デメリット、さらに「見せるだけで使えるのか?」という疑問について、公的な情報源をもとに詳しく解説します。
磁気定期券の基本的な使い方
磁気定期券は鉄道でもバスでも利用できますが、使い方の手順がICカードとは異なります。それぞれの交通機関での基本的な利用方法を確認しましょう。
※ 鉄道は自動改札への投入が原則。バスや無人駅・有人改札では「提示」での利用が基本です。
| 項目 | 要旨 | 解説 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 鉄道:自動改札での利用 | 投入口→取り出し口。 | 改札のきっぷ投入口に磁気定期券を投入するとゲートが開き、定期券は先の取り出し口から戻る。乗車駅で投入して入場、降車駅でも再度投入して出場するのが基本。 | faq.hankyu.co.jp |
| 鉄道:有人改札・無人駅での扱い | 駅員に提示。 | 自動改札がない駅や無人駅では、駅係員に定期券を提示して通過。自動改札普及前は提示が一般的だったが、現在はスムーズな通行のため自動改札通過が原則。 | Yahoo!知恵袋 / trafficnews.jp |
| バス:均一運賃路線 | 降車時に提示。 | 均一運賃の路線バスは、降車時に運転手へ定期券を提示すればOK。乗車時の処理は不要。 | kotsu.city.kobe.lg.jp |
| バス:距離制(整理券あり) | 整理券+定期券提示。 | 距離制の路線は乗車時に整理券を取得し、降車時に整理券と定期券を一緒に提示。区間確認のうえ降車できる。 | kotsu.city.kobe.lg.jp |
磁気定期券のメリット
磁気定期券にはいくつかの利点があります。ここでは代表的な3つのメリットを挙げ、その理由と根拠を説明します。
メリット1: ICカード定期券のようなデポジット不要で初期コストが安い
磁気定期券はカード発行時のデポジットが不要です。IC定期券の場合、新規にICカードを発行する際に通常500円のデポジットが必要ですが、磁気定期券ならカード代に追加の費用はかかりません。
例えば、JR西日本や私鉄各社で導入されているIC乗車カード「ICOCA」定期券を購入する場合、定期運賃とは別に500円のデポジットが必要ですが、磁気定期券であればそうした初期費用は発生しません。
このため、新しく定期券を作る際の金銭的ハードルが低い点は磁気定期券のメリットと言えます。また定期運賃そのものはICでも磁気でも同額に設定されています。純粋に通勤・通学定期の代金だけで利用を開始できるのは、学生や新社会人にとってありがたいポイントでしょう。
メリット2: 複数ICカードの干渉やタッチミスによる改札エラーが起こりにくい
磁気定期券は改札エラーの心配が比較的少ないことも利点の一つです。
ICカード定期券では、カードを読取部にタッチし忘れたり、財布に複数のICカードを入れたまま改札を通ろうとしてエラーになるケースがあります。実際、交通事業者も「ICカードを2枚同時にタッチすると改札機が正しく処理できず扉が閉まる」と注意喚起しています。
一方、磁気定期券は改札機に1枚ずつ投入して使うため、ICカードのように重ね持ちによる読取りエラーやタッチ漏れのトラブルが起きにくいのです。
改札では磁気ヘッドによる確実な読み取りが行われるため、「うっかりタッチし損ねて改札を通れない」といった事態になりにくく、確実に改札を通過できる安心感があります。
メリット3: 区間によっては新幹線を定期券だけで乗車(自由席)できる
磁気定期券には新幹線を併用できる場合があるというメリットもあります。定期券の区間内に新幹線の停車駅が2駅以上含まれる場合、別途特急券を購入すれば、その区間について新幹線の普通車自由席に乗車できます。
JR西日本によれば、在来線の磁気定期券区間に東海道・山陽新幹線の駅が含まれている場合は定期券でカバーされる区間の新幹線に乗れる仕組みがあります。この場合、新幹線区間の乗車券を別途購入する必要がなく、定期券で既に支払っている区間の運賃は免除される形になります。
必要なのは特急料金(自由席特急券)のみで、新幹線にスムーズに乗車できるのです。IC定期券についても近年は同様のサービス(「タッチでGo!新幹線」など)が拡大していますが、磁気定期券は従来から駅の有人改札で定期券と特急券を提示することで新幹線に乗るという使い方が可能でした。
急な出張や通学・通勤ルート上の新幹線利用時に、磁気定期券を持っていれば在来線区間の運賃を重複して支払わずに済むのはメリットと言えます。
磁気定期券のデメリット
便利な磁気定期券ですが、一方で次のようなデメリットもあります。ここでは重要な3点を確認しましょう。
デメリット1: 紛失や盗難時に再発行ができず損失リスクが大きい
磁気定期券最大の欠点は、なくしてしまった際に再発行してもらえないことです。IC定期券であれば、紛失時に利用停止措置を取ったうえで再発行を受けることが可能ですが、磁気式の定期券は技術的にそれができません。
JR東日本も「磁気定期券(裏面が黒いタイプの定期券)を紛失された場合は再発行を承ることができません。盗難等の場合でも同様です」と明言しています。
磁気定期券(裏面が黒いタイプの定期券)を紛失された場合は再発行を承ることができません。盗難等の理由であっても同様となります。引き続き定期券をご利用になる場合は、改めて定期券をお買い求めいただくことになります。紛失された定期券が見つかった場合、新たに購入された定期券の有効期間が10日以上残っていれば、その期間分の払いもどし手続きをいただけます。詳しくは駅係員にお尋ねいただきますようお願いいたします。
JR東日本公式サイトより引用
つまり、一度落としたり盗まれたりするとその残り期間分の定期代が丸々無駄になるおそれがあります。
ただし、後日紛失した定期券が見つかった場合、新しく買い直した定期券の有効期間が10日以上残っていればその残存期間分の払い戻しを受けられる制度はあります。それでも新しい定期券を買い直す際には再度運賃を支払う必要があるため、磁気定期券を利用する際は紛失に細心の注意が必要です。
デメリット2: 改札通過に手間がかかる
磁気定期券は改札を通る際にICカードより時間と手間がかかる点がデメリットです。自動改札機では磁気定期券を都度ケースから取り出して投入しなければならず、ICカードのようにかざすだけで通れる簡便さがありません。
ラッシュ時は一人ひとりが磁気券を挿入して取り出す動作が発生するため、IC専用改札と比べて通過スピードが遅くなりがちです。また、近年はICカード対応を優先して磁気定期券対応の改札機が減少傾向にあります。
鉄道各社は次々と磁気定期券の新規発売終了を発表しており、阪急電鉄や神戸電鉄では2025年までに全ての磁気定期券販売を終了すると公表しています。将来的には磁気券対応改札機の設置も縮小されていく可能性が高く、磁気定期券利用者は限られた改札を探して通行しなければならないケースも増えるでしょう。
デメリット3: 定期券区間外を利用する際に毎回精算が必要で煩雑
磁気定期券では、定期区間外への乗り越しをする際に自動精算がされないため、都度精算処理をしなければなりません。IC定期券の場合、あらかじめICカードにチャージしておけば、定期券区間を超えて乗車したときに自動改札機で不足分の運賃を自動精算してくれます。
一方、磁気定期券で区間外まで乗った場合は、降車駅で専用の精算機に定期券を入れ、足りない運賃を現金などで支払ってから出場する必要があります。阪神電鉄の案内でも「磁気定期券の場合、降車時に精算機にて現金等で精算してください。ICカードによる乗り越し精算は利用できません」と明記されています。例えば、定期区間外の駅で降りる際に切符を買い直すか精算する手間が毎回発生するわけです。
IC定期券なら自動的に追加運賃が引き去られるので改札を出るだけで済みますが、磁気定期券では精算の手順を踏まないと改札を通れないため、急いでいるときや小銭を持ち合わせていない場合に煩わしさを感じるでしょう。
磁気定期券は見せるだけでも使えるの?
磁気定期券は場合によっては「見せるだけ」で利用できます。駅の自動改札機ではなく有人改札を通る際や、バス・無人駅で降車する際には、定期券を係員や運転士に提示するだけで使うことが可能です。たとえば路線バスでは降車時に磁気定期券の券面を運転手に見せれば、そのまま降りることができます。
JRなどのワンマン運転の列車でも、駅に駅員がいない時間帯は降車時に運転士に定期券を見せて下車するルールになっています。
ただし、原則として駅では自動改札機に通すのが基本であり、磁気定期券を改札係員に見せるだけで通行するのは例外的な対応です。有人改札口が開いている駅では駅員が定期券を確認して通してくれる場合もありますが、自動改札のみの出口では定期券を見せるだけではゲートが開かないため通れません。
昨今は改札の省力化が進み、有人改札を設置しない出口も増えています。そのため、利用者側も磁気定期券をスムーズに使うために、極力自動改札機に通すよう心がける必要があります。
一方、ICカード定期券の場合は「見せるだけ」で使うことは想定されていません。IC定期券は改札機やバスのカードリーダーにタッチして利用するものなので、機械に触れさせないと運賃処理が行われません。例えば、名古屋市交通局は「市バス乗車の際にマナカを料金箱にタッチせず見せるだけではダメか?」との質問に対し、「必ず料金箱にタッチしてください。乗務員に見せる必要はありません」と回答しています。
ICカード定期券やアプリが主流になりそう
磁気定期券の特徴や利点・欠点について解説してきました。近年はICカード定期券やスマートフォンのアプリ定期券も広く普及しています。それぞれ一長一短はありますが、利便性の面ではIC化・アプリ化のメリットが大きいのも事実です。
特に、スマホで利用できるモバイル定期券は、カードそのものを持ち歩かなくて済むため紛失や盗難の心配が格段に低い点が魅力です。モバイルSuicaなどのサービスではデポジットも不要で、アプリ上から定期券の購入・継続やチャージが可能なので、券売機に並ぶ手間も省けます。
ICカード定期券同様に区間外乗車の自動精算にも対応しており、紙の磁気定期券にはない便利さと安心感があります。もっとも、スマートフォンの電池が切れると改札を通れなくなるリスクや、対応機種の制限など留意点もあります。しかし各社ともモバイル定期券のサービス拡充に力を入れており、今後ますます使いやすくなるでしょう。



コメント